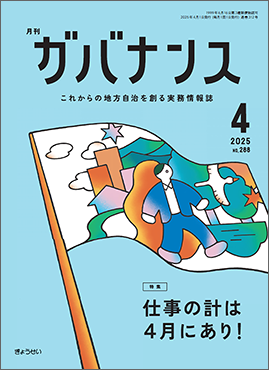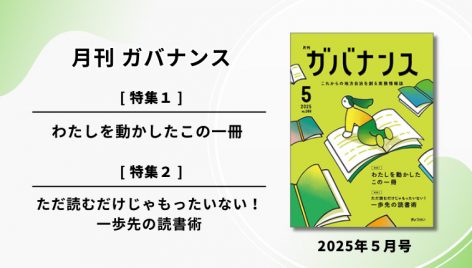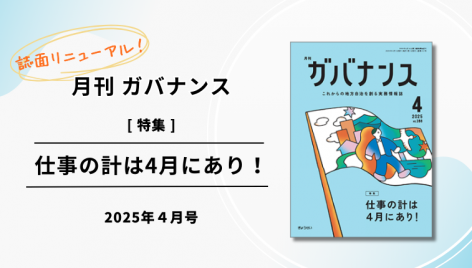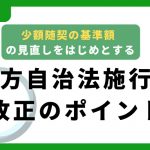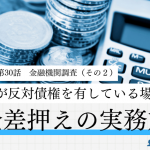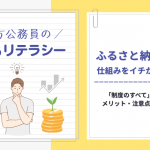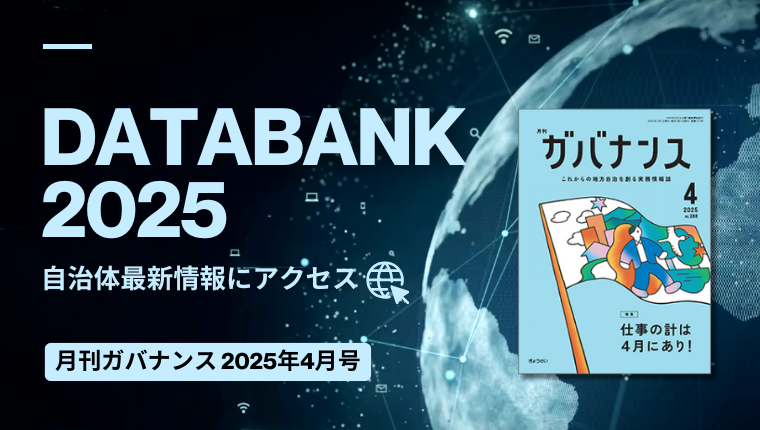
自治体最新情報にアクセス DATABANK
自治体最新情報にアクセス|DATABANK2025 月刊「ガバナンス」2025年4月号
地方自治
2025.05.08
目次

出典書籍:月刊ガバナンス 2025年4月号
●無電柱化条例を制定・施行
神奈川県鎌倉市(17万5600人)は、「鎌倉市無電柱化条例」を制定した。条例は全8条で、電線類の地下埋設で無電柱化を図り、都市の防災機能の向上と安全・円滑な交通の確保、景観の保全に資することが目的。既に無電柱化されている市道の①JR鎌倉駅周辺の小町通り約600mと②JR大船駅周辺の芸術館通り等約500m及び無電柱化が予定されている③深沢地域整備事業区域約31haの無電柱化路線・区域内に電線類を敷設する場合は、地下に埋設することを義務付けた上で、違反等に対して、是正のための措置を勧告でき、勧告に従わない場合は公表できると規定している。
道路上の電柱や電線は、景観を損なうのみならず、歩行者や車椅子使用者等の通行の妨げとなる。また、地震時には倒壊した電柱が緊急車両等の通行を阻害するおそれがあり、長期停電のリスクも高まる。そのため、市は2024年11月に「無電柱化推進計画」を策定。無電柱化推進の基本的な方針を定め、無電柱化候補の対象路線を選定して2034年度末までに無電柱化手法を検討するとしている。
条例は2025年4月1日の施行。今後、無電柱化が完了した路線を条例の対象にする考えで、無電柱化を維持していく。
(月刊「ガバナンス」2025年4月号・DATA BANK 2025より抜粋)
●上下水道事業の包括的民間委託を実施
宮城県利府町(3万5900人)は、安心・安全な上下水道サービスを提供するため、2025年4月1日から上下水道事業の包括的民間委託を開始した。町で導入した包括的民間委託は、これまで業務ごとに別々の民間事業者に委託していた業務を、一つの民間事業者に一括して委託する手法。今回は上下水道サービスの「水道施設維持管理業務」「公共下水道施設維持管理業務」「料金徴収・窓口関係業務」「コンサルタント業務」を一括して、2035年3月31日までの10年間委託した。委託先は、㈱日水コン・㈱データベース・㈱宅配・㈱NSCテックが出資企業となり、町内に新たに設立された特定目的会社の㈱Rifレックス(リフレックス)。なお、保有資産を民間事業者に移し、運営権も民間事業者が有する「民営化」とは異なり、資産移譲は行われず、運営権は利府町にある。業務を包括的に委託して官民連携で業務を進めていく形なので、包括的民間委託移行後も、料金設定や施設の整備方針の決定・実施など上下水道事業の根幹部分は従来どおり町が担う。
町の上下水道は建設投資が概ね完了し、今後は管路や施設の耐震化と老朽施設の更新を進めていくことになる。それに伴って多額の費用が見込まれる一方、節水機器の普及等により給水収益等は減少傾向にあり、また、近年の物価上昇の動向により、長期的に安定した事業経営が困難になることが予想されている。包括的民間委託は、そのような状況を迎えても町民の生活に直結するライフラインを持続可能にすることを目指したもので、①多岐にわたる業務を広い視野かつ長期的な視点で把握し、民間事業者の工夫による業務の効率化、②維持管理と更新計画の支援を一体で実施することによる費用の最適化、③民間事業者の活用による人材確保と確実な技術継承――が図られると期待されている。
(月刊「ガバナンス」2025年4月号・DATA BANK 2025より抜粋)
●公立高校入試に「学校設定枠」を新設
新潟県(213万7700人)教委は、2027年度県公立高等学校入学者選抜(2024年度の中学1年生が受検)から選抜制度を変更することとした。中学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行を踏まえ、スポーツや科学の分野等での優秀な成績の生徒が対象の推薦入試「特色化選抜」を廃止。その一方、一般選抜に、すべての学校・学科で設定する募集枠の「一般枠」に加え、新たな募集枠として「学校設定枠」を設けた。中学生がより主体的に高校を選択できるようにするのがねらい。
「学校設定枠」は、アドミッション・ポリシー(各高校が策定したスクール・ポリシーの一つで、入学時に期待される生徒像)を踏まえ、各高校の校長の裁量で設定できる募集枠で、同枠を設定した学校・学科で選抜を実施。志願者は「一般枠」に加えて同一校に出願でき、「調査書の各教科の学習の記録」「学力検査の結果」「その他の検査等(学校ごとに定める提出書類、面接等)の結果」を総合的に判断して選抜する。「学校設定枠」を設定するかどうかや、設定する場合の募集人数、その他の検査等の内容は各高校が定める。学校・学科ごとの選抜方法等は26年3月までに公表する。
(月刊「ガバナンス」2025年4月号・DATA BANK 2025より抜粋)
●再配達削減に向けて動画などで啓発
佐賀県(80万1100人)は、宅配事業の再配達削減に向けた取組みに力を入れている。運送業者の時間外労働の上限が24年度から原則として年間960時間に短縮されたことを受け、物流適正化のための対策を講じなければ、輸送能力が不足し物流が滞ることが懸念されている。こうした「物流の2024年問題」への対策として、県は宅配の再配達の削減に向けて利用者の意識や行動を変えていくためさまざまな啓発を実施。
利用者にできることとして、①配達状況の通知サービスに登録②相手が受け取れる日時・場所を指定③確実に受け取れる時間・場所を指定④コンビニやロッカー置き配の利用⑤宅配ボックスの設置⑥複数の荷物はまとめて受け取りの6点を特設サイト等で紹介したほか、ヤマト運輸㈱、佐川急便㈱、日本郵便㈱と協力し、チラシ「不在連絡票を受け取られた方へ佐賀県からのお願い」を作成、周知を図るなどした。
また、県WEBサイト上の「再配達削減のためのお願い」において、県が今までに制作し、テレビ等で放映してきたCM5篇(「プレゼント」「家まで届かない」「待ちぼうけ」「食べられないパン」「仕送り」)を視聴できるようにした。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00399702/index.html
(月刊「ガバナンス」2025年4月号・DATA BANK 2025より抜粋)
●「ちばDXポータル」開設で県と市町村のサービスを一元化
千葉県(631万200人)は、県と県内すべての市町村のオンライン申請の窓口等を集約したポータルサイト「ちばDXポータル」を開設、2024年12月3日から公開している。
「千葉県全体のオンラインサービスの入口」「県のDX関連施策の見える化サイト」と位置付け、県民や事業者にとって手続きがしやすい環境づくりを進めることを目指している。
サイトの大きな柱は次の四つ。①「手続したい」(各市町村のオンライン手続きのページにアクセスできるほか、県のオンライン手続を「税金」や「福祉」などのジャンルから探せる)、②「相談したい」(LINEやZoomなどで、気軽に相談できるサービスを集約)、③「知りたい」(デジタル技術の導入に関する助成金やイベント・研修などの情報を掲載)、④「千葉県のDX推進の取組」(県のDX推進の取組状況などを「暮らし」「仕事・いきがい」「産業」「行政」「スマート県庁の推進」に分けて紹介)。
このほか、県のDX関連の取組みを利用者のインタビューを交えて紹介するDX推進PR動画も視聴することができる。
https://www.pref.chiba.lg.jp/dejisen/dxportal/index.html
(月刊「ガバナンス」2025年4月号・DATA BANK 2025より抜粋)
●経済産業省創設の「おもてなし規格認証」を取得
北海道小樽市(10万6500人)の市役所本庁舎は、おもてなし規格認証機構の審査を経て、「おもてなし規格認証」の「紺」認証を取得した。「おもてなし規格認証」は、日本のサービス産業と地域経済の活性化を促進するため、サービス品質を「見える化」する制度として経済産業省が創設して2017年度から認証を本格スタートし、現在、おもてなし規格認証機構が審査・認証などの制度の運用を行っている。認証は、支店など事業所単位で行い、ランクの高いほうから「紫」(期待を大きく超える「おもてなし」提供者)、「紺」(独自の創意工夫が凝らされたサービス提供者)、「金」(お客さまの期待を超えるサービス提供者)の3段階となっている。
小樽市内ではオール小樽でおもてなし力を向上するため、小樽観光協会が中心となって2024年度から地域独自の認証制度として「小樽おもてなし認証」を始動。良質なサービスの提供・維持・向上に向けて、小樽らしさを強みにして顧客体験価値を高められる事業者を認証している。市はその動きに呼応し、経済産業省創設の「おもてなし規格認証」取得を目指して本庁舎の職員の研修や職場環境の改善に取り組んだ結果、2024年11月30日付けで認証を取得した。自治体の認証取得は全国初。
今後は、本庁舎勤務の職員は引き続き「おもてなし」を意識して更なる市民サービス・接遇のレベルアップに努めるとともに、本庁舎勤務以外の職員にも広げ、「おもてなし都市・小樽」を目指して市民目線に立った市政を推進するとしている。

(月刊「ガバナンス」2025年4月号・DATA BANK 2025より抜粋)
●「要介護認定業務のデジタル化」モデル事業の実証を実施
大分県(111万2800人)は、大分市・別府市とともに、国の「要介護認定に関する自治体業務等のデジタル化」モデル事業に取り組んでいる。自治体や医療機関等のシステムを2024年度中に国が整備する介護分野のPMH(介護保険に係る情報を自治体・利用者・介護事業者・医療機関などで連携するシステム)と情報連携させることで、要介護認定に関する一連業務をデジタル化し、利用者へのサービス改善と自治体職員の負担軽減を図るのがねらい。大分県が大分市・別府市と共同で国のデジタル田園都市国家構想交付金に申請して採択され、医療機関や介護事業所など関係機関の協力を得て、要介護認定に係る関連業務のデジタル化を全国に先駆けて進めている。
具体的には、①認定調査、②主治医意見書、③認定審査会開催、ケアプラン作成における④ケアマネジャーからの開示請求、サービス提供に向けた⑤資格等情報の確認――といった一連の要介護認定業務において、①を紙からタブレットに、②の提出を郵送から電送に、③を紙や対面での実施からデジタル資料やオンラインでの開催に、④と⑤の紙での請求・開示作業をWEB上で閲覧できるようにする。
大分県・大分市・別府市は国のモデル事業に取り組むにあたり、各情報の電送化に伴うシステム改修作業や連携テストなどの実証の準備を進めた上で、2025年1月中旬から、大分市の5医療機関・5介護事業所、別府市の2医療機関の協力を得て、国の構築するシステムを活用したデータ連携の実証を開始。大分市では①と③は独自に取り組んでいたことから②④⑤について、別府市では③④⑤は独自に取り組んでいたことから①②について、新たに体制を整備し、2025年2月末まで実証を行った。
今後は、効果と課題を国に報告するとともに、県内他自治体に取組みの横展開を図っていく。
(月刊「ガバナンス」2025年4月号・DATA BANK 2025より抜粋)