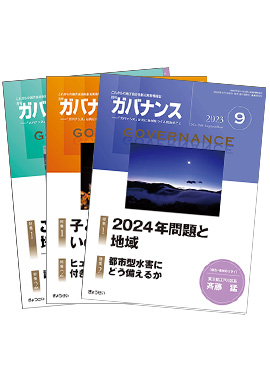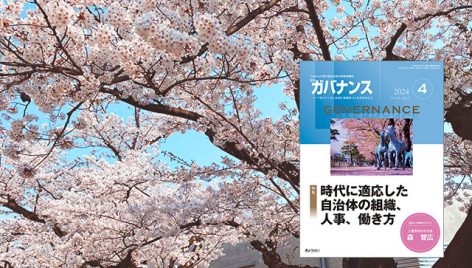新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第49回 避難指示解除への指示のミライ
時事ニュース
2024.01.23
本記事は、月刊『ガバナンス』2017年4月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
はじめに
2011年3月以来継続している福島第一原子力発電所のINES(国際原子力事象評価尺度)レベル7苛酷事故(以下、フクシマ事故)に起因する放射能汚染(核害)によって、自治体の一部区域または全域に避難指示区域が設定された。避難指示区域が設定されると居住が禁止されるため、住民は長期の強制「避難」を余儀なくされた。フクシマ事故の収束(「廃炉」ともいう)の見込みは今も立っていない。
しかし、事故発生6年目を迎え、3月末ないし4月初に、浪江町・富岡町・飯舘村の帰還困難区域を除く全域と、川俣町山木屋地区の避難指示を解除する見込みである(注1)。そこで、今回は避難指示解除について検討してみよう。
注1 避難指示解除は、これまでも逐次行われてきている。なお、政府は、避難指示解除準備区域及び居住制限区域においては、各市町村の復興計画等も踏まえ遅くとも事故から6年後(2017年3月)までに避難指示を解除し、住民の帰還を可能にしていけるよう環境整備を加速するとしていた(2015年6月12日閣議決定)。そのような既定路線に乗った対処といえよう。
避難指示解除の意味

避難指示解除がされると、住民の「帰還」が可能になるというのが、国の見解である。しかし、これは、帰還の定義によっては、必ずしも正しくはない。なぜならば、避難指示区域のなかの居住制限区域・避難指示解除準備区域においては(注2)、除染事業・復興拠点整備事業あるいは事故処理事業などで(注3)、すでに実際に多くの人々が活動している。住民には一時帰宅や準備宿泊も認められてきている。つまり、避難指示解除によって可能になる「帰還」とは、継続的に夜間居住するという意味に過ぎない。
注2 ただし、帰還困難区域では立ち入りは認められない。
注3 内閣府原子力被災者生活支援チーム「避難指示区域の見直しについて」(2013年10月)によれば、避難指示が解除されなくても、居住制限区域・避難指示解除準備区域では、立入、特例宿泊、準備宿泊、企業誘致、既存事業再開、営農・営林は、可能という。できないことは、自宅等での宿泊のみである。
もっとも、このように避難指示解除がされると、住民「帰還」が可能になるだけではない。全国から、誰でも継続的に夜間居住ができるようになるわけである。
除染事業・復興拠点整備事業・事故処理事業、さらには、今後の復興事業・行政業務によって、「しごと創生」がなされる場合には、就業のために転居して来る事業系住民が出てこよう。避難指示解除の本質とは、住民「帰還」を可能とすること以上に、事業系住民が転入することを可能にすることである。
住民帰還を可能にする対処方策

国や被災自治体は、「依然として放射線量の高い区域の避難指示をなぜ解除するのか」という住民の疑問に対して、「帰りたい住民もいるから」という説明をする。帰還・移住・長期避難・待避・通所という住民の一人ひとりの希望に応えるという建前から、「帰還」を希望する人が、たとえ少数であってもいる場合には、それに応えるという理由である。こう言われると、長期避難や待避・通所を望む住民も、あえて、「帰還」希望者の意思を阻害してはならないという思いやりから、納得をする。しかし、この理屈付けは必ずしも正しくはない。
なぜならば、「帰還」=(夜間継続居住)を可能にするという目的だけならば、一般的に、「帰還」を希望しない住民に対しても含めて、区域ごとに面的に避難指示解除をする必要はない。「帰還」を希望する住民に、個別の居住を点的に「許可」すればよい。正確に言えば、「帰還」を希望する住民にのみ、個別の者を名宛てして、地域を指定して、「必要がなくなった」避難指示を解除すればよい。
原子力災害対策特別措置法第27条の2第1項で「原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体を当該原子力災害から保護し、その他当該原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる」(下線筆者)が、同第5項で「市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない」だけである。
避難指示解除は安全宣言ではない

面的に避難指示解除しないなかで、個別の希望者に応じて、個別地域ごとに判断して点的に市町村長が避難指示解除をすることは、あたかも、一般的に安全性を認めていない区域に、個別に「帰還」を認めるように見える。すると、不安全を放置することと受け取られかねない。
しかし、避難指示解除は、市町村長が安全性を保証したものではない。いわば、避難指示は「赤信号」ではあるが、避難指示解除は「赤信号」の消灯である。信号がない交差点は、安全性が保証されない。「帰還」する住民の個人に、安全性の確保の責任が転嫁されるだけである。
もちろん、避難指示解除を「青信号」のように、希望的に解釈することもできよう。しかし、「青信号」ですら「安全だ」「進め」を意味するものではなく、「安全を確認した上で進んでも可い」と言うだけである。避難指示解除も、「帰還せよ」という意味ではないのはもちろん、安全であることすらも意味せず、「安全を確認した上で帰還してもよい」ということに過ぎない。
従って、希望者にのみ個別に避難指示を解除するのは、「帰還」を求める住民の希望に添っただけである。しかも、一般的に避難指示を解除しなくても、住民間で不公平ではない。希望しない人に個別に避難指示解除をしなくても、何も不都合はないからである。そもそも、帰還・移住・長期避難・待避・通所という住民の一人ひとりの希望に応えるという建前を貫徹するならば、避難指示解除/継続も、住民の一人ひとりの希望に応じればよい。希望しない人には避難指示を継続すればよい。
おわりに

国は17年3月末までの避難指示解除を目標に設定していて、ほぼ、そのように「復興」日程を統制してきた。飯舘村長に対しては16年6月17日付で、川俣町長に対しては同年10月28日付で、居住制限区域及び避難指示解除準備区域について、避難指示を17年「3月31日午前0時をもって解除し、居住者等に対してその旨周知すること」と、原子力災害対策特別措置法第20条第2項にもとづいて、原子力災害対策本部長(同法第17条第1項により首相が宛て職)の名義で指示が発出されている(注4)。
注4 本稿校正中の2017年3月10日に、浪江町長および富岡町長宛に、原子力災害対策本部長から、避難指示を解除せよとの指示が発出された。
同法第20条第2項は、「原子力災害対策本部長は、(中略)緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、(中略)必要な指示をすることができる」とする。しかし、避難指示解除で可能になることは「帰還」=継続夜間居住に過ぎず、原子力災害事後対策(法第27条)「を的確かつ迅速に実施するため特に必要がある」ものではない。国が市町村長に避難指示解除を指示するという集権的介入は、住民一人ひとりの意向を尊重する点からも適切とは言えない。
加えて、市町村長が国からの指示なくして自主的に行うとしても、避難指示解除は、安全性という観点からは、何も保証しない。従って、避難指示解除をしても、核害被災からの回復を何ら意味しない。また、希望者の「帰還」という観点からも、市町村長が希望者にのみ個別に避難指示解除をすればよい。
面的な避難指示の一律解除は、「帰還」を希望する住民にも、不要である。また、「帰還」を希望しない人にもプラスにもならない。避難指示解除が将来の賠償の打ち切りに繋がるのであれば、全ての住民にとってマイナスしかない。
このようななかで、被災自治体の役割は、小さくはない。本来は一般的・面的な避難指示解除は不要である。国の指示によって避難指示解除をさせられても、それは安全を保証しないことを、確認し続けることである。避難指示解除は、積極的に「青信号」を点灯するものではなく、単に「赤信号」を消灯しただけである。被災自治体は、正しく発信していくことが必要である。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)など。