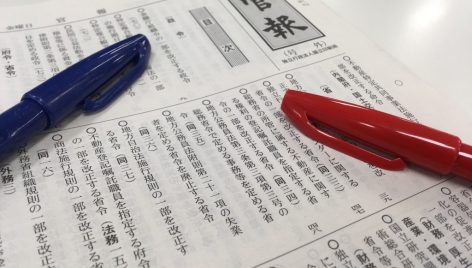『増補改訂 財務3表一体理解法』(國貞 克則/著)―決算書を読み解きその意味を知る
キャリア
2019.12.16
第12回 決算書を読み解きその意味を知る
役所の会計は、現金主義・単式簿記により行われています。これを「お小遣い帳のようなもの」と揶揄する向きがあり、何やら一段低いもののように考えたがる人もおられるようですが、私はそうは思いません。公会計と企業会計では、それぞれの果たすべき役割が異なりますので、どちらかが優れているという問題ではないと考えます。
ただ、従来の公会計制度においては、資産や負債の把握が十分ではなく、コスト情報も不足している部分があるのも事実でした。そこで、国が先導する形で「統一的な基準による地方公会計」の整備が進み、多くの自治体がホームページに公表しています。
この取組みが、要した手間とコストに見合うだけの効果を上げていけるかどうか、正直なところ、私はやや懐疑的に見ています。しかし、どちらにしても作ることになったのですから、できる限り活用していかなければ、まさに骨折り損のくたびれ儲けということになってしまいます。とはいえ、無理に使おうとして、さらに労力をかけるのもなんだかおかしな話ですので、意味のある活用をしていきたいものです。
そのためには、「統一的な基準」がどのようなものなのかしっかり把握するとともに、企業会計についての理解も欠かせないと思います。
そこで、今回は國貞克則さんの『財務3表一体理解法』を紹介します。企業会計の仕組みを理解するための入門書として非常に有名な本ですので、お読みになった方もおられると思います。実は國貞さんは、公認会計士でも税理士でもありません。つまり、会計の専門家ではないのです。だからこそ、初学者にもわかりやすい本が書けたのかもしれません。企業会計を理解するための最初の一歩として読み、理解したつもりになった段階で、再度読み直したい一冊です。

○簿記を知らなくても決算書は読める
「会計」や「決算書」といった言葉を聞いて、「難しい」「ややこしい」と瞬間的に感じてしまうという方もおられるのではないでしょうか?「借方」「貸方」といった独自の表現に煙に巻かれてしまううえに、簿記から始めなければ本質的なところは理解できない、という空気が、一層ハードルを高くしているように思います。
もちろん、簿記は会計の基本中の基本ですから、これをきちんと理解し、仕訳もできるようになることが望ましいことは言うまでもありません。しかし、決算書を読む、会計を理解する、ということに特化するのなら、簿記ができるかどうかは必ずしも必須条件ではありません。
この本が長く支持されているのは、簿記を使わずに決算書を作成していくことにより、会計の基本的な仕組みをわかりやすく説明しているからでしょう。タイトルにあるように、3表、つまり「損益計算書」「貸借対照表」「キャッシュフロー計算書」を一体的に作成していくことにより、それぞれのつながりをとらえ、決算書の構造を理解できるように工夫されています。決算書を読む場合の目の付け所についても解説していますので、この一冊を読むことで、企業の決算書の概略がつかめるようになります。
〇企業の決算書は操作されていることが少なくない
役所が決算書を操作したら大変です。信頼を損なう不届きな行為として、大きな批判を受けるでしょう。
それは企業でも同じであるように思えるかもしれませんが、國貞さんは、「損益計算書や貸借対照表は操作されているものがけっこうあります」と言い切ります。これは國貞さんの持論というわけではなく、企業会計を知っている人なら、常識の部類かもしれません。上場企業ではあまりないことかもしれませんが(それでもちょくちょく粉飾決算などが報道されています)、中小企業では、税金を払わないで済むように黒字を縮小させたり、銀行への見栄えをよくするために赤字を出さないようにしたり、いろいろな操作が行われます。そして、そうした操作ができるのが企業会計の特徴でもあります。
決算書を見る際に心得ておくこととして、「キャッシュは事実、利益は意見」という有名な言葉もあります。発生主義、複式簿記、などと聞くと、厳密なもののように思いがちですが、実際はその反対であることは押さえておきたいところです。

〇企業と役所の決定的な違い
企業も役所も、永続するべき経営体です。にもかかわらず、役所だけ現金主義・単式簿記なのはおかしいとの批判が根強くあります。
企業と役所が同じ目的で行動し、同じようにお金を調達し、そのお金を増やすべく活動し、それによって経営しているのなら、同様の決算書類が必要でしょうが、実際には両者は全く異なっています。
著者は、「会社というものはどんなビジネスを行っていても、その基本的な活動は皆同じ」と指摘します。そして、その活動は、「お金を集めてきて」「そのお金を何かに投資し」「利益を上げる」ことだと言います。
では、役所はどうでしょう。「お金を集めてきて」までは似ていますが、その使い道としては「何かに投資する」ことがメインではなさそうです。むしろ、戻ってくることが全く想定されない支出をすることがほとんどでしょう。最後の「利益を上げる」という点は、役所の活動には基本的にはありません。つまり、当然のことながら、企業と役所では目的も行動内容も全く違うのです。
企業会計は、企業の活動の結果をわかりやすく示すために工夫されています。そのため、目的の異なる役所の活動を示すためには、適していない面があると考えるのが自然でしょう。
〇違いを知ったうえで、決算書を読む・活用する
企業の決算書は、数百ページにもなる役所の決算書と違ってかなり薄いものです。しかし、そこからいろいろな情報を読み取ることができます。具体的には、負債と資産の関係や、売上高と利益の関係、資産と自己資本の関係などから、「成長性」「収益性」「安定性」を見極めることができます。
決算書の分析方法を理解することは、役所に関係のある企業の経営状況を知るためにも、個人的に投資を考えるうえでも、とても重要なことだと思います。しかし、これらの指標が公会計の分析でも使えるかというとそんなことはありません。ここまで読んでいただいておわかりのとおり、企業と役所は全く違うからです。違うものを同じ尺度で測ろうとしても、意味のある結果は導き出せません。
この本を読むと、企業会計の仕組みがよくわかると同時に、企業と役所の仕事の進め方の違いも、改めて理解することができます。
企業会計の要素を加えた公会計の決算書作成は始まったばかりです。企業と役所の違いを知ったうえで、意味のある活用方法を模索していきましょう。
【今月の本】
『増補改訂 財務3表一体理解法』(國貞 克則/著)
(朝日新聞出版、2016年、定価:820円+税)