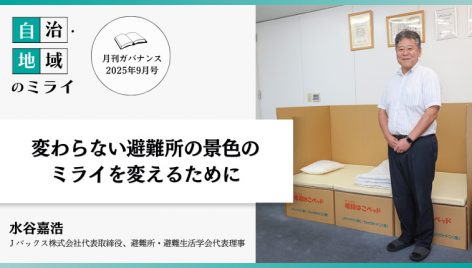自治・地域のミライ
自治・地域のミライ|「移動」という視点から地域社会の未来を見つめる 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 研究員・講師 伊藤 将人
地方自治
2025.11.28

出典書籍:月刊『ガバナンス』2025年12月号
★「自治・地域のミライ」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!
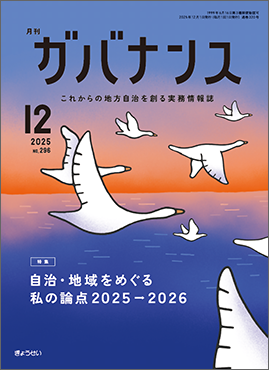
月刊 ガバナンス 2025年12月号
特集:自治・地域をめぐる私の論点2025→2026
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター
研究員・講師
伊藤 将人
2024 年より、国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)で研究員・講師を務める伊藤将人氏。地域社会学、地域政策学を専門に、「移動」という視点から地域社会のこれからを見つめている。普段、誰しも日常的に、自分の意思で移動しているようでいて実は階層や性別、住む地域でその自由や経験には大きな差がある──。そのことを詳らかにした書籍『移動と階級』で話題の、若き研究者に地域のミライをどう見ているか聞いた。

東京・六本木の国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)で。1991年に国際大学(IUJ /新潟県南魚沼市)付属の社会科学系研究所として設立。ミッションは「学術研究と実践活動の両輪により情報社会を進化させる」。研究活動と併せて政策提言にも力を入れる。
自分事、そして地域事として、「未来」を考えていかなければならない
地元での原体験
――主な研究分野は、地域政策学や地域社会学。今の研究をするまでの経緯は。
私は1996年3月生まれの29歳。小学校入学前後に、全国的に土日が休みの完全週休2日制になった。いわゆる“ゆとり教育”ど真ん中で学校時代を過ごしてきた。
長野県松本市で生まれ、北安曇郡池田町で育った。池田町は比較的社会的な活動や生涯教育に熱心な地域だった。月に1回、土曜日に公民館が主催する地域塾︵ふるさとチャレンジ塾︶が開かれ、地域の高齢者のところへボランティアに行ったり、自然体験をしたり、地元の工業高校で何か作ってみたりなど、地域に開かれていた。
そういった地域や社会的な場が、私にとってとても居心地がよい「サードプレイス」だった。中学生になっても関わり続け、地元に関わるって面白いなと感じるようになっていた。
高校に進学、当初は大学に行くつもりはなかった。公務員コースに入って、将来は地元の公務員になろうと思っていた。当時の自分には、長野から出るという選択肢はなかった。
それまで地元で享受する側だったので、次は何かをやる側になろうと思い、選択したのが地元の大学の社会福祉学部だった。社会福祉の文脈から、例えば社協やケアマネージャーなど含めて様々な形で地域に関われたらいいなと思っていた。しかし、いざ入ってみると、自分より向いてる人がたくさんいるということを感じた。
大学に進学したのが2014年。まさにその年に地方創生が始まった。授業でも地方創生が扱われ、関心があった。大学があった上田市は、新幹線で東京から約1時間。移住者も多く、地方で何かクリエイティブなことをしよう、イノベーティブなことをしようという人と会う機会が増えていった。もともと考えていた公務員のような形ではない地域との関わり方があるのだと知るきっかけになった。
学生時代は、地元で仲間と一緒にフリーペーパーの発行など地域活動もした。フリーペーパーは卒業後も継続し、9年ぐらい続いた。実践的に地域に関わることが面白いと思った大学時代だった。
しかし徐々にずっと地元だけでよいのかとも思うようになった。周りに目を向けると留学している人もいる。私も一念発起して文科省の助成金を申請し、ぶどう農家でアルバイトをしたお金で、半年間イギリスに留学した。
現地では、観光・まちづくりに関する勉強や調査などをした。地元での実践を離れて知識や刺激をインプットする時間だった。そのときに、書籍や論文などを読んでいくと、現場で実際に動いていたときに感じていた課題やモヤモヤが、実は論文などで過去に解のようなものが示されているということを知った。さらに、日本では先進的だと思っていたけれども実は海外では10年前に同じような課題に直面していて、すでに解決している例なども知った。
そのときに、学術的なものや海外の事例と、国内や地元の現場の間をつなぐ人の存在が、今後必要になってくるのではないか、と感じた。これが研究者を志したきっかけだった。
“移住”“移動”から社会を見つめる
――その中でも「移住」や「移動」にフォーカスしている。
地方移住や移動のように、人々が行き交う中で、地域というものが存在しているという前提で研究をしてみようと考え始めたのが、2019~2020年頃だった。地元で目にした移住者と地元の人の関係性、そして移住定住政策などに関心を持ち、帰国してから大学院に進学し、初めて地元・長野を離れて東京へ出て、研究生活を始めた。
――関心を持った時期がまさにコロナ禍。
東京に出てきたものの、コロナ禍で大学に行くことが難しくなり、長野に戻る頻度も高かった。
コロナ禍で特に浮き彫りになったのが、テレワークやリモートワークをできる人や自治体と、それができない人や自治体には大きな断絶があるのではないかということだった。うまく対応できているほうが、外からの制度や人を上手く受け入れている気がした。その理由や構造は何かということに関心を持った。
社会学や政策学、その中でもグローバルよりもよりローカルな地域社会学、地域政策学を研究してきた。これまでの、地域や農村の社会学では現場に行き、当事者の声を聞くというミクロな話が多かった。しかし、社会経済や政治的な流れなどの中で人々は生き、地域も存在している。ミクロなものとマクロなものを両方つないでみる、そこをわかりやすく説明する、解きほぐすことが社会学的な地域研究の醍醐味であると感じていた。
――「移動」の研究は過去にもあったのか。
日本においても「移動」的なものの研究をしている方はいた。大きい2つの流れとしては、「交通」系の研究と「移民、難民」研究のような国境を越える移動に関するものだ。しかし、移動というのはバリエーションがある。私が研究してきた地方移住も、確実に社会や地域に大きな影響を与えている。単なる交通や移民の研究ではなく、行っているのは「移動」という視点から世界を見つめ直す、モビリティーズ・スタディーズと呼ばれる分野だ。
これまでは、特定の地域などを考えるときに明確な境界線があった。しかし、時代が変わっていく中で、境界線が薄れ、この地域に関わる、自治を担っている人が、決してそこに定住している人だけではなくなってきている。定住のように固定的で動かないものを前提に地域や社会を考えていること自体に、もしかしたら見落としているものがあるのではないか。「移動」を軸に地域や社会を見ていくことの学術的、そして政策的な社会要請が高まっているのではないかと思っている。

いとう・まさと
1996年、長野県出身。博士(社会学)。一橋大学大学院社会学研究科、日本学術振興会特別研究員を経て2024年より現職。専門は地域社会学・地域政策学。研究分野は、地方移住・移住定住政策研究、地方農山村のまちづくり研究、観光交流や関係人口など人の移動と地域に関する研究。多数の地域連携/地域活性化事業の立ち上げに携わり、フリーペーパー事業など長野県地域発元気づくり大賞を受賞。朝日新聞や毎日新聞をはじめ、メディアにも多数出演・掲載。主な著書に、『移動と階級』(講談社現代新書、2025年)、『数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション』(学芸出版社、2024年)など。最新刊『戦後日本の地方移住政策史―地域開発と〈人材〉
創出のポリティクス』(春風社)を2025年11月に上梓。
関係人口をどう考えるか
――今年はこれまで以上に政策的に「関係人口」という言葉に注目が集まった。どのように見ているか。
マクロな視点で見ていくと、戦後日本における地方振興や地域活性化は広い意味でいうとハードの「地域開発」だった。そして、この地域開発の歴史は、日本国内の人材をどのように配置するかの歴史だった。
移住のような発想が出てきたのは90年代に入ってから。「Iターン」という言葉が出てきた。
2008年に田舎で働き隊ができ、2009年には地域おこし協力隊が創設された。この頃を境に政策は大きく転換した。リーマン・ショックや東日本大震災などでライフ・ワークスタイル観が変化し、若年層に対して移住してもらう、人材として活躍してもらうという期待と理想化が高まった。これを一番ブーストしたのが「地方創生」だった。
東京には比較的若い人が転入してくるので、彼らが地元や地方に行くことは、東京一極集中の解消にもつながる。地方の子どもがいないという問題も、若い人が移住してくれれば解決できるかもしれない。さらにその中にイノベーティブな人々がいれば、地方で起業をしてくれるかもしれない──という期待が高まったのがこの10年の地方創生だった。
この時期の特徴は、先進的な自治体のモデルを水平波及させるという方法。先進的であること自体がすごく有利に働いていた。そして、横に波及させた時点で、それはまちづくりとしてイノベーティブではなくなってしまうというジレンマを抱え、移住も人口の奪い合いになってしまう──という中で出てきたのが「関係人口」だった。
2015年の第二次国土形成計画から2023年の第三次国土形成計画にかけて分析をしてみた。「移住」という単語の登場回数が減り、そして「関係人口」がはるかに上回る回数登場するようになった。政策的にも「関係人口」の流れが来ていることがはっきりとわかる。
モビリティーズ・スタディーズの観点では、「移動」を土台に、もしくは移動性が高いことを前提に政策をつくることが社会的、学術的にも関心が高まっていると見ている。
しかし一方で、関係人口には主体性の問題もある。自発的に地域に関わるような人だけではなく、例えば高齢の親の介護のために定期的に特定の地域に行くような人もいる。このような人たちも関係人口と考えることができる。このような人たちをどう包摂するか、私たちのような立場から量的・質的に研究をして可視化し、政策現場に届けていく必要があると感じている。
――5月に発刊した『移動と階級』(*)が話題を呼んでいる。
私が研究している「移動」は、それができるかできないかが個人の自由などと密接に絡み合っている。住んでいる地域やジェンダー、年齢、国籍、そして階層や階級を含めてその価値観や考え方が「移動」というものを巡って規定されているということが見えてきた。同じような悩みを抱えている人がいるということは、制度的、社会的に解決すべき課題なのかもしれないということを感じていた。「移動」とは個人的なものではなく、社会的で政治的なものであるということを軸にまとめた。
特に女性の読者を中心に、ジェンダー的な観点からの反応が多い。この書籍では、新しいものを提示するよりも、皆がモヤっと抱えているものを可視化して社会的な課題なのだと問題提起できたことが大きかったのではないかと感じている。
*『移動と階級』(講談社現代新書、2025年)

調査研究だけでなく、実践も欠かせない。伊藤さんの地元長野県や国際大学のある新潟県南魚沼市など全国各地をフィールドにしながら実践知を深めている。
未来の主流化
――自治・地域のミライをどう描くか。
これから日本全体が縮小していく中で、何を残すか残さないかについて、住民主導で民主主義的に意思を反映していくことは重要だ。しかし、地域と関わる中で感じるのは、その地域を背負って立つような若手や子育て世代などのリーダーシップを発揮できる人たちに、かなりの負担が集中してしまっている実態がある。同じ人が様々な場面で活躍している。ある種の属人性は、中長期で地域のことを考えるとリスキーだ。
住民も加わった協議会などは今後様々な分野で増えていくだろう。そのときに、それらの会議体を構成するメンバーが、自然と近い人たちになっていくかもしれない。そのときに果たして自治のあり方として正当なのかということも、今後の5年、10年、20年というスパンで考えたときに重要な問題になってくる感じている。
最近、私が大切だと思っていることに「未来の主流化」と呼んでいるものがある。自治体の計画や戦略、ビジョンなどと呼ばれるものは、基本的には未来のことを考えている。
しかし、昨今の状況を踏まえると、未来は大事だけれども、目の前の課題にフォーカスしてしまい、これについて考えなければならない状況に置かれている人がたくさんいる。大前提としてSDGsや少子化対策などをなぜやっているのかというと、それは、私たち現代世代が未来世代への責任を負っているからだろう。例えば私たちの代で木を全部伐採してしまっていいとか、地域は私たちだけで使い尽くしてしまっていいという考え方をしているのであれば、SDGsや地方創生を目指すというような発想はそもそも生まれてこない。私たちは未来に向けて残すことは大事だということをあまり意識もせずに思っているのだ。
しかし、昨今の計画やビジョンを見ると、どこか数字合わせのようになり「未来」をしっかり見つめているのか、疑問に思うときがある。30年、50 年、そして100年も、遠いようであっという間に過ぎ去っていく。自分事として、そして地域事として、「未来」の観点をしっかり考えていかなければならない。そしてそれを私は、どういうふうにやっていくのかを、政策的、そして哲学的な観点から言語化し、現場の皆さんとも協働していきたいと思っている。

(取材・構成/本誌 浦谷收、写真/五十嵐秀幸)
★「自治・地域のミライ」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!
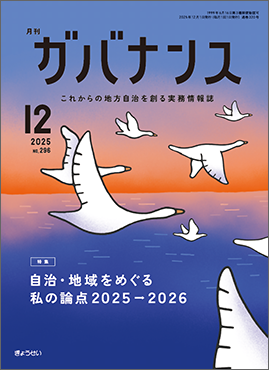
月刊 ガバナンス 2025年12月号
特集:自治・地域をめぐる私の論点2025→2026
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫