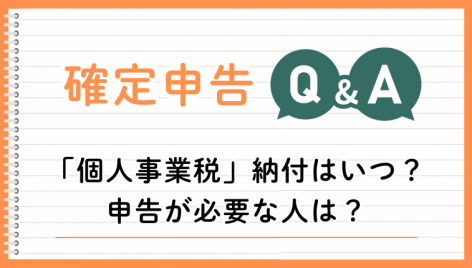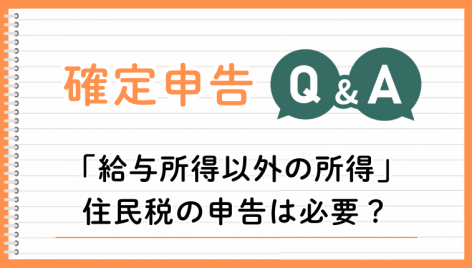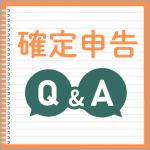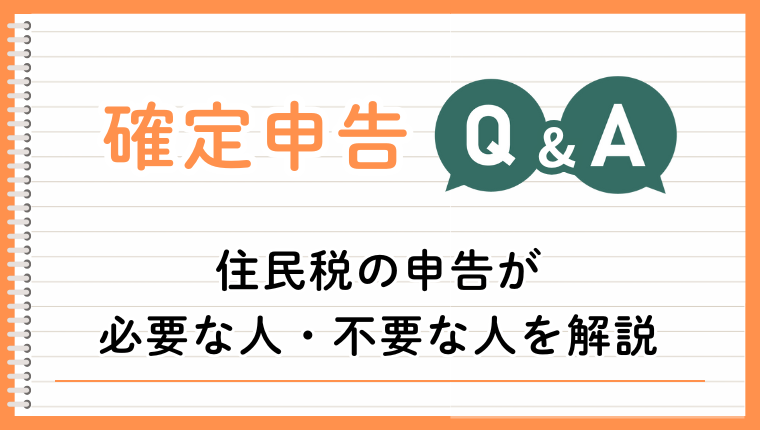
確定申告Q&A
【確定申告Q&A】住民税の申告が必要な人・不要な人を解説
地方自治
2026.01.30

出典書籍:月刊『税』2026年2月号 別冊付録「地方税務職員のための 令和7年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
確定申告に向けて知っておきたい「こんな場合は?」をQ&Aでご紹介。
地方税務職員に長く参考書として使用されている「地方税務職員のための 令和7年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」(月刊「税」2026年2月号
別冊付録)より引用しています。
この記事では、住民税の申告が必要な人/不要な人について解説します。
★本誌はこちらからチェック!

月刊 税 2026年2月号
別冊付録:地方税務職員のための令和7年分
確定申告期税務相談窓口対応の手引き
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:3,410 円(税込み)
詳細はこちら ≫
住民税の申告を必要とする者及び必要としない者

住民税の申告書は、市町村に住所を有する全ての住民が提出しなければならないのですか。それとも、所得税のように、国内に住所を有する住民のうちで前年中の所得が給与所得のみであった者、年金所得者でその収入金額が400万円以下の確定申告不要制度適用者等については、提出の必要はないのでしょうか。

市町村内に住所を有する者は、毎年3月15日までに住民税の申告書を、その年の1月1日現在の住所地の市町村長に提出しなければならないとされている。この中で所得税の確定申告書を提出した者は住民税の申告書を提出したものとみなされるので、住民税の申告書を提出する必要はない。
なお、給与所得又は公的年金等に係る所得のみの者や市町村の条例で定める者については、申告義務は免除されているので、住民税の申告書を提出する必要はない。

1 住所を有する者の申告義務
市町村内に住所を有する者は、住民税の申告書(地規第5号の4様式)を、原則として毎年3月15日までにその年の1月1日現在の住所地の市町村長に提出しなければならないとされている(地法317の2)。
この中で、所得税の確定申告書を提出した者は、それをもって住民税の申告書を提出したものとみなすこととされているため、改めて住民税の申告書を提出する必要はないとされている(地法317の3①②)。
2 申告義務が免除される者
次の者については住民税の申告義務が免除されているので(地法317の2①)、住民税の申告書を提出する必要はない。
ア 給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から
1月1日現在において「給与」又は「公的年金等」の支払を受けている者
で、前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の
所得を有しなかったもの(確定申告書の提出によって、各種所得控除及び
税額控除の適用を受ける者を除く)
イ 所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち、市町村の条例で定めるもの
これについては、「均等割の非課税限度額以下の者」と定められている。
アの該当者について
給与や公的年金等の支払者から市町村長あてに給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されること等により(地法317の6①③、321の7の3)、本人の申告を待たずに他から住民税の課税資料が得られる者であることにより、申告書の提出義務が免除されている。
イの該当者について
住民税の課税資料の提供の必要のない者として、申告書の提出義務が免除されている。
例外について
【1】
前年中の所得が給与所得のみであった者及び前年中の所得が公的年金等に係る所得のみであった者が、以下の適用を受けようとする場合は、3月15日までに
「給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告書(地規第5号の5様式)」
「寄附金税額控除申告書(一)(地規第5号の5の2様式)」
「寄附金控除申告書(二)(地規第5号の5の3様式)」又は
「給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書(地規第5号の6様式)」
を提出しなければならない(地法317の2③)。
雑損控除額、医療費控除額、寄附金税額控除、純損失又は雑損失の繰越控除
【2】
前年中の所得が公的年金等に係る所得のみであった者が、以下の適用を受けようとする場合は、3月15日までに一般の「住民税の申告書(地規第5号の4様式)」を提出しなければならないとされている(地法317の2①③⑤)。
社会保険控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寡婦控除額、ひとり親控除勤労学生控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、特定親族特別控除、雑損控除額、医療費控除額、純損失又は雑損失の繰越控除、寄附金税額控除額
【3】
申告義務の申告書の提出義務のない者であっても、前年中に純損失又は雑損失の金額のあるものは、これら繰越控除を受けるためには連続してこれら事項を申告しておかなくてはならないので、3月15日までに住民税の申告書を提出する必要がある(地法317の2④)。
3 申告書の提出義務者
ア 確定申告書を提出した者:提出不要
所得税確定申告を提出した者は、申告手続の簡素化を図る趣旨から、住民税の申告書を提出したものとみなすこととされているため、改めて、住民税の申告書の提出をする必要はないとされている(地法317の3①②)。
そして、その確定申告書に記載された所得税に関する事項のうち住民税に相当するもの及びそれに付記された次の事項については、住民税の申告書に記載されたものとみなすこととされている(地法317の3②③)。
確定申告書の附記事項は次のとおりである(地規2の3)。
① 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 ② 給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収の 方法 ③ 前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を住民税 につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名、個人番号 及び青色専従者給与額 ④ 前年中に非居住者であった期間を有する場合においては、所得税法第164条第2項各号に掲げる国内源泉所得の金額 ⑤ 前年分の所得税につき控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業 専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては氏名及び住所) ⑥ 所得税において確定申告をしないことを選択した未上場の少額配当等 に関する住民税の総合課税の特例を受ける金額 ⑦ 寄附金税額控除額の控除に関する事項 ⑧ 一定の配偶者及び扶養親族について次の事項 ㋐住民税の納税義務者(前年の合計所得金額が1,000万円以下である ものに限る)の自己と生計を一にする配偶者(退職所得を有する者であって、前年の合計所得金額が133万円以下であるものに限る)の氏名、生年月日、個人番号並びにその者の前年の退職所得を除く合計所得金額。ただし、申告者と別居している上記配偶者についてはその配偶者の住所、国外居住者である配偶者についてはその旨 ㋑住民税の納税義務者の扶養親族(退職所得を有するものに限る)の 氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号並びにその者の前年の 退職所得を除く合計所得金額。ただし、申告者と別居している扶養親 族についてはその扶養親族の住所並びに国外居住者である扶養親族に ついてはその旨 ⑨ 扶養親族(16歳未満の者に限り、前記⑧㋑の者を除く)の氏名、申告 者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、 氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養 親族については、当該扶養親族の住所並びに控除対象外国外扶養親族で ある場合には、その旨 ⑩ 特定親族(退職手当等に係る所得を有する者に限る)の氏名,申告者 との続柄,生年月日及び個人番号並びにその者の前年の合計所得金額並 びに申告者と別居している特定親族については,当該特定親族の住所並 びに国外居住者である特定親族については,その旨 ⑪ 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)の氏名、生年月日及び個人 番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び生年月日)並びに申 告者と別居している同一生計配偶者については、当該同一生計配偶者の 住所並びに控除対象外国外同一生計配偶者である場合には、その旨
イ 確定申告書を提出しなかった者:提出が必要
所得税確定申告書を提出しなかった者(住民税の申告を必要とする者)は、申告義務を免除される場合を除き、住民税の申告書を提出する義務があり、この申告書の記載事項は以下のとおりである(地法317の2①)。
① 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 ② 青色専従者給与額又は事業専従者控除額に関する事項 ③ 青色申告の場合の純損失の金額の控除に関する事項 ④ 青色申告をしない者に係る変動所得の計算上の損失の金額若しくは被災事業資産の損失の金額又は雑損失の金額の控除に関する事項 ⑤ 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除に関する事項 ⑥ 寄附金税額控除額の控除に関する事項 ⑦ 扶養親族に関する事項 ⑧ ①から⑦までのもののほか、賦課徴収について必要な事項
特定の控除を受けるためには、損失明細書、繰越控除明細書又は外国税額控除に関する明細書を提出する必要がある。
▼「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」では、他にも以下のような解説を確認できます。
住民税の申告について
・住民税の申告書を提出する必要性
・申告書の提出期限及び提出先
・所得税の確定申告が不要で、住民税の申告が必要とされている
もの
・給与所得者が雑損控除等を受ける場合の申告
・公的年金等受給者が雑損控除等を受ける場合の申告
・赤字が生じた年の翌年の申告
「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
全目次はこちら!(PDF)
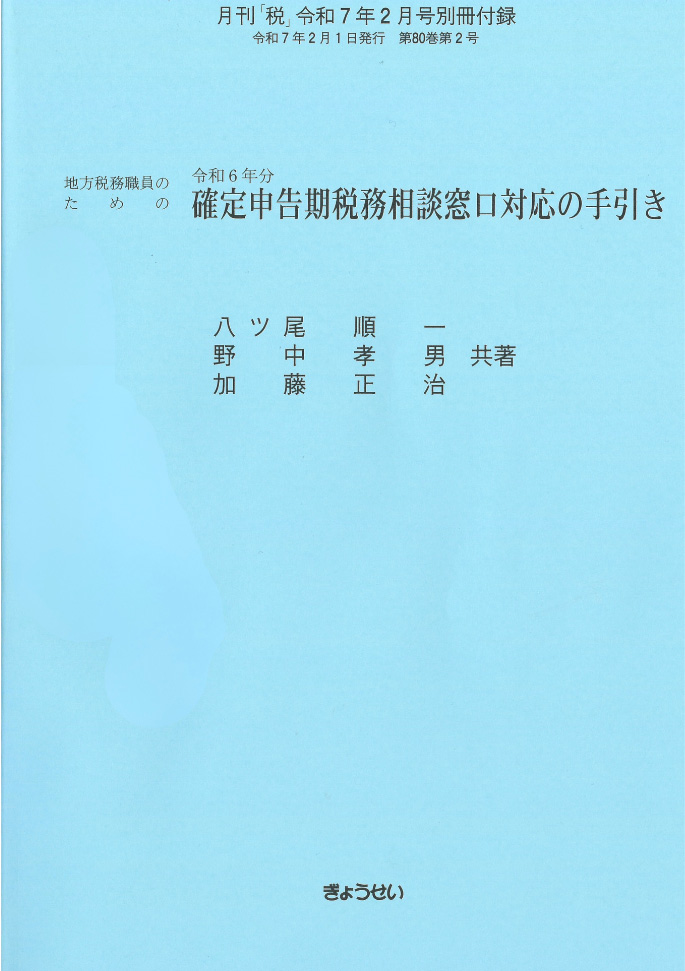
★本誌はこちらからチェック!

月刊 税 2026年2月号
別冊付録:地方税務職員のための令和7年分
確定申告期税務相談窓口対応の手引き
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:3,410 円(税込み)
詳細はこちら ≫