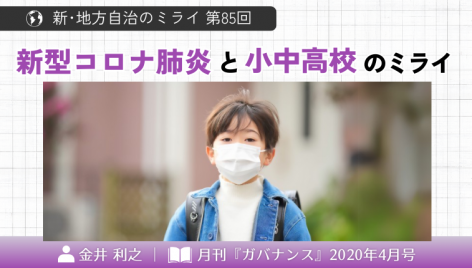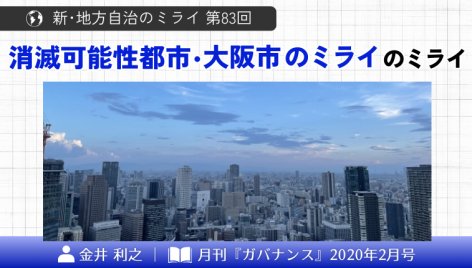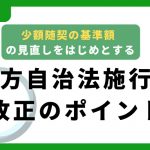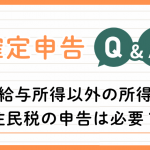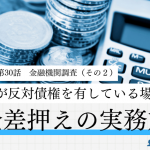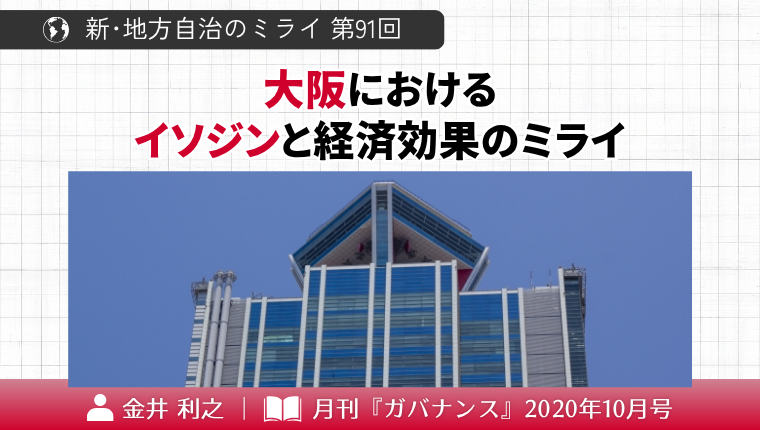
新・地方自治のミライ
大阪におけるイソジンと経済効果のミライ|新・地方自治のミライ 第91回
地方自治
2025.07.14

出典書籍:『月刊ガバナンス』2020年10月号
★「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
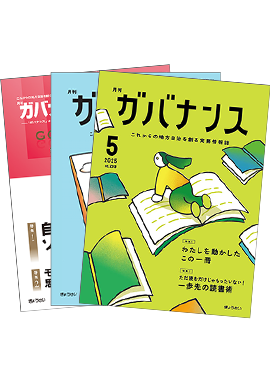
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2020年10月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

2020年8月4日に、吉村洋文・大阪府知事は、ポピドンヨード入りのうがい薬(イソジンなど)で新型コロナの重症化を抑える趣旨の記者会見を行った。一部専門家の「効果」の主張を安易に利用してしまった(注1)。この「効果」は専門家によって誤りが早急に正された。しかし、同様の「効果」の主張は、他にも見られる。
注1 毎日新聞デジタル版2020年8月9日21時11分配信。
それは、『大都市制度(総合区設置及び特別区設置)の経済効果に関する調査検討業務委託報告書』(注2)(嘉悦学園、2018年6月29日(注3)、以下、『報告書』)である。大阪都構想(=大阪市廃止・特別区設置)で、10年間で1兆円を超える「経済効果」があるとした。大阪市解体に向けた吉村知事側の「メリット」の「論拠」となっている(注4)。そして、2020年11月1日に大阪市廃止市民投票が行われる(注5)。『報告書』については、すでに様々な論評があり(注6)、重複する面もあるが、あえて採り上げてみよう。
注2 大阪市ホームページ掲載。2019年8月28日第25回大都市制度(特別区設置)協議会、資料1。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/cmsfiles/contents/0000478/478997/03shiryo1(0219.0601teisei).pdf
注3 その後、誤りが指摘され、2020年2月19日、6月1日に訂正されている。
注4 産経WESTデジタル版2020年6月19日17時30分配信。
注5 日本経済新聞デジタル版2020年9月7日10時20分配信。
注6 例えば、村上弘「「大阪都」=大阪市廃止・特別区設置の経済効果」『立命館法学』2018年4月号(380号)など。
『報告書』の要旨

『報告書』の分析は2本柱である。第1は、「政策効果分析による特別区の経済効果」であり、大阪市を4特別区に分割する直接の効果である。
①基礎自治行政の財政効率化効果
②二重行政解消による財政効率化効果
③府市連携による経済効果
の三つである。第2は、
④「マクロ計量経済モデルによる経済効果」
である。以下、順に要約しよう。
①は、人口規模が過大な大阪市を分割すると、効率が向上するという。同一の行政水準を達成するときに、基礎的自治体の人口規模を横軸にすると住民一人あたりの歳出がU字型曲線となっており、人口規模は大きすぎても小さすぎても非効率という議論である。『報告書』によれば人口約50万人が最も効率的であるから、10年間で1兆円程度の効果が見込まれた。
②は、大阪府と特別区の役割分担が明確になり、二重行政が解消されるという。病院・大学を統合すると、規模の経済で効率化するという。現状では二重行政解消には府市合意が必要だが、大阪都構想では特別区の権限がなくなり、府区間合意が不要で政策実現性が高い。こうして、40億円から70億円程度が見込まれる。
③も、大阪都構想では府区間合意は不要なので、府市連携のような合意形成の協議・調整で「遅れ」は発生せず、鉄道整備などで適切な社会資本整備ができ、4800億円程度の経済効果が発現するという。
④では、東京に比べて大阪の社会資本の限界生産力が約半分と低いが、二重投資の解消、大阪市域内への積極的投資、広域での最適化によって、5000億円から1兆1000億円ほど期待されるという。
以下では、これら①~④を検討してみよう。
効率的特別区の架空性
①は全く成り立たない。第1に、事務権限の大きな大阪市を解体し、事務権限の小さい4特別区に分割すれば、歳出は減るのは当然である。同一行政水準での比較になっていない。
第2に、特別区が失う事務権限が、大阪府に移管されれば、大阪市民から見れば行政水準は改革前後で同一である。それならば、経済効果分析には、大阪府の歳出増加を積算しなければならない。見える削減部分だけを示して、隠れた歳出増加を提示しないのは、不誠実だろう。
第3に、U字曲線論は、社会経済的な都市化による歳出ニーズの増大や、人口規模に応じた権限の拡大などの要因をも含んでおり、推計はほとんど無意味である。また、虚心坦懐に見れば、U字曲線ではなくL字曲線である。大阪市がL字曲線から上方に位置する「外れ値」なのは、大阪という大都市社会のニーズを反映したものであろう。これは、特別区になっても変わらない。そして、その基礎的自治体としての事務を大阪府が担うならば、大阪府の「外れ値」的な歳出増加になる。なお、『報告書』のU字曲線論を前提にすれば、人口規模の大きな大阪府は、基礎的自治体の事務を担うには、大阪市より非効率であり、さらに歳出増加は膨らむ。
二重行政論の架空性
②は、本当に無駄ならば、無駄だと思う側が一方的に削減できる。府市合意の必要はない。一方的に廃止しないのは、無駄ではないと、両者が判断しているからである。
現状の行政水準維持を前提に、規模の経済を追求するためには、府市合意が必要であろう。この点は③とも関わる。ただ、重要なことは、病院や大学を名目的に統合しても、実際のサービス現場は分散しているので、医療教育従事者・事務職員を減らせない。減らせば同一行政水準は維持できない。
大阪府単独決定の架空性
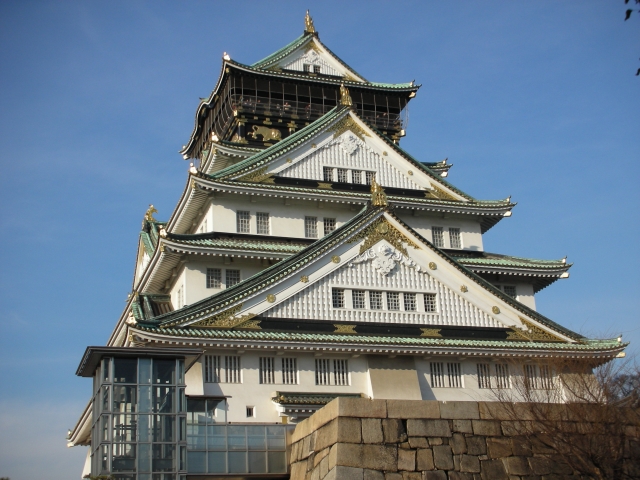
②③は、府市両首長の方向性が異なると連携ができないが、大阪市を解体すれば、大阪府が、特別区の意向を無視して、組織統合や社会資本整備できるという。府市連携ではなく、実態は大阪府単独決定である。
しかし、第1に、各種事業が複雑に絡み合い、地元地区住民・地権者の意向が重要な社会資本整備では、公式の事務権限の所在とは無関係に、国・広域自治体・基礎的自治体の合意形成が不可欠である(注7)。そして、現在の府市2首長ではなく、府区5首長との合意形成が必要であることを意味する。
注7 東京都と23特別区の関係はそうである。
第2に、1団体による単独決定が望ましい経済効果を生むとは限らない。より大きな無駄と失敗が可能になる。経済効果の分析には、失敗確率や被害最小化などリスク回避判断も必要である。
東京並みの限界生産力の架空性
④は皮算用(うまいもうけばなし)にすぎない。第1に、①の財政効果額を社会資本整備に投入するから、①と④とは両立しない。現行の大阪市民への行政水準を下げて、開発投資すると言っているのと同じだからである。
第2に、無駄な社会資本整備は、限界生産力を低下させる。経済効果が生じるかは、政策判断の是非次第であり、失敗確率を見込む必要がある。③と同様である。
第3に、大阪の特有事情である。大阪府の人口比重は非大阪市域にあるので、大阪府は大阪市域外住民の利害に従って政策決定をする。東京都は特別区部が多摩地区より人口が大きいので、東京都は区民の利害を優先する。しかし、大阪府は逆である。大阪市域外への投資(「二元行政」と同じ)、または、大阪市域への迷惑施設投資(例えば、カジノ・軍事基地など)になろう。
おわりに
『報告書』のいう大阪都構想の経済効果は怪しく、利害計算のできる大阪市民ならば、恐らく納得しないだろう。得する人は賛成するが、損する人が反対するのは、自然である。
しかし、政治の妙味は、利害計算を超えて、「大義(もっともらしいはなし)」や「印象操作(イメージ)」や空気・感情や人リーダーシップ気を使って、損する人に賛成させることにある。また、損することを知らせなければ、莫然とした「信用」で賛成するものである。経済取引でいえば詐欺的行為を、「正当(クレバー)」に行うのが為政の本質である。例えば、周辺部が衰退するのに、周辺部町村民を合併に賛成させる。将来的に故郷に住めなくなる危険施設を誘致させる。ギャンブル依存症が増えるのにカジノに手を挙げさせる。富裕層優遇「改革」を貧困層に支持させる、などである。
右肩下がり社会では、利益の分配はできず、負担・危険・不利益の押し付けへの同意調達が求められがちである。為政者は、損する人に賛成させたがる。大阪市民も、大阪の「維新」の大義や空気などのために、損に合意する機会が与えられる。もちろん、事後的に損したと気付いたときに、大阪市域外転出できれば、大阪市域で生活する不利益を被ることは避けられる(注8)。
注8 市民投票において、利害計算ができずに選択に失敗しても荒廃した大阪市域から転出して不利益を回避できる人と、市外転出できずに利害計算のできなかった選択の失敗の不利益を被る人と、自身は利害計算できるが他者の利害計算の失敗の所為で市外転出できずに不利益を被る人とが、同じ一票を持つ。
なお、本論は、学者個人の独立した立場での見解であり、筆者が務めている各種職務や職務に関係する団体の見解とは全く無関係である。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
★「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
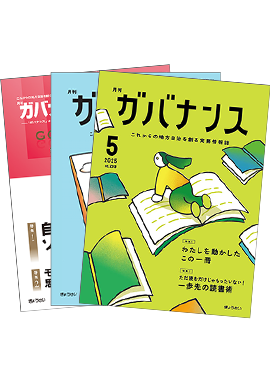
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫