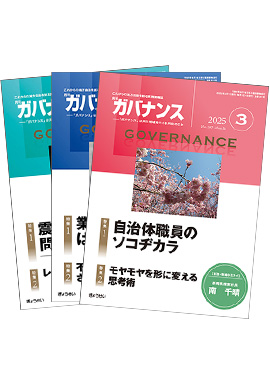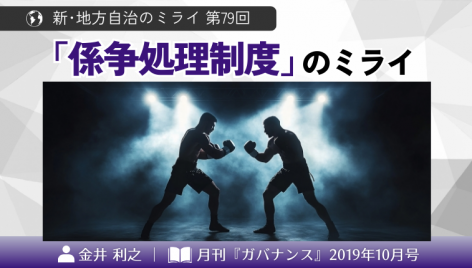新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第84回 納税・寄附・売買とふるさと納税のミライ
地方自治
2025.05.19
本記事は、月刊『ガバナンス』2020年3月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

2020年1月30日に、大阪高等裁判所は、総務省が泉佐野市に対して、ふるさと納税対象団体に指定しなかったことに対して、総務省の全面勝訴の判決を行った。判決の法的評論は法律家が行うだろうから、本論ではふるさと納税制度を通じて自治の原理を考察してみよう。
ふるさと納税の論理
判決によれば、「元々寄附者が居住地の地方団体の減収をもたらすものであるという問題を含んだ制度である上、これに返礼品競争が加わることにより、地方団体全体の財源の総額の増加が見込まれないのに、返礼品の調達費用を含む募集経費としてそこから流出する金額がますます増加し、結果として本来の特色ある事業などの公の支出に充てることができる総額も減少するという事態を招くもので、これを根本的に是正するには、本件制度の廃止か、返礼品の禁止という措置を採るほかない」(判決76頁、以下同様)という。これは納税の論理であり、政府セクターの論理である。
しかしながら、2019年税制改正によるふるさと納税指定団体制度は、ⓐ「本来の制度趣旨」とⓑ「地場産品を返礼品とすることによる地域産業奨励の効果など」を維持する「政策的判断」から導入されたという(76頁)。ⓑについては、売買の論理であり、経済セクターの論理である。ⓐについて判決は別の箇所で、「寄附という経済的利益の無償供与という法的枠組み」(75頁)や「本件制度の基本的な枠組である寄附の枠組み」(76頁)などと述べているように、寄附の論理であり、社会セクターの論理のことである。このように、ふるさと納税は、納税=政府の論理、寄附=社会の論理、売買=経済の論理が、実態として混在している。
いわゆる「三つのセクター」論からも、世の中の活動に三つの側面があるのは、自然の現象である。もっとも、政府セクターに属する自治体が、社会と経済の論理に引きずられるのは、そもそも、政府としての存在意義を失わせる。
ふるさと納税は寄附の論理か

判決によれば、ふるさと納税制度は「民間の公益活動を支えるとの考えの一環として、民間による自発的公益活動促進やこれへの寄附金税制等の改革と併せて、個人の住民税の地方団体に対する寄附金税制の拡充のなかで、納税者側の自発的意思で納税先を選択して地方団体を応援できれば納税意識の涵養や地方自治の充実に資するとの考え方に立脚し、希望する団体に対し寄附をする形で住民税を納付する仕組みとして構想され」(73~74頁)たという。ここから、ふるさと納税制度の趣旨や法的枠組は、寄附の論理だと導いた。
しかし、判決が述べているように、ふるさと納税は自発的意思による納税先の選択にすぎず、民間の公益活動を促進するものではない。実際、ふるさと納税=寄附先は自治体であって、民間公益活動が増えるわけではない。ふるさと納税制度の効果は、「寄附者が本来納税すべき住所地の個人住民税の一部が、寄附金を受領した地方団体にそのまま移転する」(38頁)という、自治体間の税収の分配だけである。しかも、納税意識の涵養や地方自治の充実が目的であり、完全に政府(特に地方政府=自治体)の論理である。
立案段階での「ふるさと納税研究会」でも、
①納税意識の涵養
②ふるさとの大切さを意識
③受入側の地方団体における自治意識進化
④納税者と地方団体の間の新たな関係
などが指摘されており(34頁)、地方政府の論理である。但し、納税分割方式では、課税権やその強制性、住民間の公平性などの問題を克服しにくいので、「寄附金税制を応用する方式」となった(35頁)。要するに、寄附の論理は便法・便宜にすぎず、制度の本質や趣旨では全くない。
確かに、返礼品を期待しない寄附の論理に見えるかのような現象もある。例えば、被災自治体へのふるさと納税は広く見られる。しかし、災害に関する様々な寄附・義捐金やボランティアは存在する。ふるさと納税は、非災自治体の税収を被災自治体に振り向けるだけであり、ボランティアの総量が増えるわけではない。自治体職員が被災地に応援に行ったり、災害のために特別交付税を厚く配分する(特別交付税総額は一定なので非災自治体の取り分が減る)などと同じことである。
ふるさと納税は売買の論理か

第2に、判決が記載した立案過程からも明らかなように、「地域産業の奨励」などの売買=経済の論理は全く存在しない。もちろん、全ての政策・制度は、私利私欲のなかに放り込まれるので、人々や民間団体が合利的に行動するのは織り込み済みではある。むしろ、そうした合利的行動があっても、制度・政策の趣旨である論理(ここでは納税=政府の論理)を実現できるように設計すべきである。自治体に期待されたのは、「従前以上に地域の活性化のための方策に取組み、その情報発信」をする「善政競争」(36頁)の結果としての地域産業の活性化であって、公金による地場産品の買上という管理統制経済ではない。
政府セクターである自治体が、利己的に行動して売買の論理に転落することは、およそ自治体である以上、自滅行為である。自治体には、「自治の良識」(36頁)、「自制」(37頁)、「節度ある運用」(40頁)が求められて当然である。判決は表面的・便法的な寄附=社会の論理に立った上で、「寄附金が経済的利益の無償の供与」であることから、過剰な返礼品に否定的であるが、実は、納税=政府の論理においても結論は同様になる。納税額に応じて返礼品が納税者に提供されてはならない。
ふるさと納税騒動の帰結
ふるさと納税は、本来は納税=政府の論理から始まったが、便法として寄附=社会の論を借りて制度化した。しかし、寄附文化のない日本では、必ずしも爆発的に使われることはなかった。その後、ふるさと納税のパンデミックを引き起こしたのが、返礼品の突然変異である。こうして、実態では、ふるさと納税は、大都市圏富裕層による節税と格安ネットショッピングという売買=経済の論理に囚われてしまった。
合利的行動を人々が行うのは、税制や経済政策ではありふれたことである。しかし、利己的行動を織り込んで公益性を確保すべき自治体が、自らの節制を失って、あたかも利己的企業になってしまった。そこでは、ふるさと納税額を掻き集めることは「稼ぐ自治体」として正当化され、地場産品の公金買上が地域活性化にも繋がるとされた。このように、近年の自治に蔓延る利己的行動原理、売買=経済の論理、すなわち、自治体の企業化が、ふるさと納税騒動を引き起こしてきた。そして、自治体が合利性で凝り固まったがゆえに、総務省はもはや返礼品を禁止できない。自治体は、納税=政府の論理を見失い、売買=経済の論理に囚われてしまい、いわば自治体であることを放棄しつつある。
個別自治体の立場からは、返礼品の掻き集めは、当該自治体の財政状況にも、地域経済にも効果があるとして、正当化される。しかも、利己的行動は「寄附」という非営利・ボランティアの粉飾のもとで行われる。寄附文化は未熟なままで抑圧され「奇附」化した。さらに、自治体全体の税収は減少する。また、ふるさと納税の税収で目玉政策が実現できたと自治体が宣伝すればするほど、目玉政策は富裕層の寄附次第となり、自治体としての政策優先度の判断の責任放棄が容易になる。自治体の利己的行動の結果として、自治の役割が干涸らびて行く。
泉佐野市が頑張れば頑張るほど、自治の自壊への道を開く。確かに、泉佐野市の「跳ね上がった」売買の論理は否定されたかもしれない。しかし、その背後で横並びの「節度」をもって行動する多数の自治体に、売買=経済の論理は「健全」(57頁)に静かに深く広がった。「存立の危機にある」(54頁)のは、ふるさと納税制度ではなく、公益を担う政府としての自治体なのである。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。