
自治体の防災マネジメント
白保地区みんなで助かる津波避難〜石垣市白保地区防災計画〜│自治体の防災マネジメント 第109回
地方自治
2025.11.19

この記事は3分くらいで読めます。

出典書籍:『月刊ガバナンス』2025年4月号
★「自治体の防災マネジメント」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!
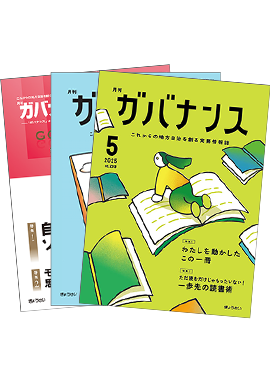
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
※写真はイメージであり、実際の土地とは関係ありません。
本記事は、月刊『ガバナンス』2025年4月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
白保地区の津波
1771年4月、八重山諸島を大津波が襲った(明和の大津波)。このとき、石垣島の白保村(現在の石垣市白保地区)では1574人の住民のうち1546人が亡くなり、生き残ったのは28人という壊滅的被害を受けた。あまりの被害の大きさに、波照間島から446人を移住させて再興に努めた。
現在は、明和の大津波のときとほぼ同様の約1500人が住んでいて、住民の津波避難意識は非常に高いといわれている。白保地区の津波被害想定は、第1波到達が最速で8分、最大遡上高が約30mとされる。一方、海岸付近から、安全とされる場所までは徒歩でおおよそ30分、車で約5分かかる。
地区防災計画モデル事業への取り組み
日本時間2024年4月3日8時58分に発生した台湾花蓮県沖の地震により、石垣市には9時1分に津波警報が発令された。このとき、白保地区をはじめ多くの地域で車避難による渋滞が発生し、避難に時間がかかった。この教訓から、石垣市は白保地区をモデル地区として地区防災計画を作成し、他地区にも水平展開したいと考え、内閣府の地区防災計画作成モデル創出事業に応募し、採択された。
津波避難が徒歩では完全に間に合わないことから、車避難を前提に地区防災計画を作成したいとのことであった。地区全体で車による津波避難を取り上げた地区防災計画は初めてではないだろうか。実際、高齢者等の要配慮者がいる場合、または津波避難場所まで遠い場合に、車避難は必ず発生する。それなら、「原則として徒歩避難」のスローガンにこだわらず、車避難により全員が助かる可能性を追求したいものだ。
地区防災計画WSの経過
白保地区では地区防災計画作成のため、2024年度、全体として次に示すような3回のワークショップ、1回の避難訓練を実施した。
・第1回WS(24年11月16日):津波避難の課題、対策を抽出
・津波避難訓練(24年12月1日)
・第2回WS(24年12月14日):アイデア出し
(1)避難のタイミングと持ち物
(2)車での避難場所・避難ルート
(3)高齢者等の避難支援
・第3回WS(25年2月22日):集合知を形成
第1回ワークショップ
24年11月16日、白保公民館で第1回WSを行った。筆者らが津波防災の基本的な話をした後、参加者は東日本大震災時の津波避難の経験談を読み、「課題」「対策」「へぇーと感じたこと」を思いつくままにポストイットに記入した。その後、9班(各班平均4人)に分かれ、ワールドカフェ方式で津波避難の課題、対策などを話し合い、各班が3~5つの対策をまとめた。
ワールドカフェは、原則として4人程度がまじめなテーマで雑談をしながら、気づきを深める手法である。
・まず、災害時の生のインタビュー(エスノグラフィー)、新聞記事など、災害時の状況をイメージし、共感を醸成する素材を読み込み、気づいたことをポストイットに簡単にメモする。
・1回目の話し合いでは、グループメンバーが互いにポストイットを模造紙に貼りながら、KJ法により全体の課題感を共有する。
・2回目は、グループで一番おしゃべりだった人を残し、ほかの3人がバラバラに別のテーブルに移動する。そこで、ほかのグループのメンバーと意見交換し、気づきを深めていく。
・3回目は、もとのテーブルに戻り、それぞれ別のメンバーと話し合った際の気づきを紹介して共有する。その後、課題を解決するための具体的なアイデアを3~5点紡ぎ出す。
・その後、参加者全員がほかのテーブルのアイデアを見て、効果的なもの、ユニークなものに赤丸シートなどを貼って評価する。
・最後に講師が、赤丸シールがたくさん貼ってあるものを紹介し、共有を深める。
第1回WSのポストイット、アイデアを時系列的に課題分析すると、「個人の防災意識を高める」「津波避難」「避難生活に必要なもの」が導き出された。
津波避難訓練
24年12月1日、石島市で総合防災訓練が行われ、白保地区は津波避難訓練を実施した。車両が124台、バイク5台、自転車2台、徒歩67人が訓練に参加した。ほとんどが最速の津波到達時間である8分以内に避難できたというから驚きだ。

24年12月1日の津波避難訓練時の車両。相乗り避難を意識している。(石垣市提供)
アンケートには、「訓練では消防団などが誘導したが本番では誘導者がいなくなる」「独居老人をどう避難させるか」「標識があるとわかりやすい」「車をとめるスペースなどがあまり十分でないため、バイクや自転車などでの避難も考えていきたい」「車両で避難する人は徒歩で避難している人と相乗りができるようにしたほうがいい」など多くの意見が寄せられた。
第2回ワークショップ
24年、12月14日、「津波避難」をテーマに、6班に分かれてグループワークを実施した。時間内で議論を収束するために、前回のWS、避難訓練でのアンケートを踏まえて次の論点を示したうえ、各論点について20分程度グループで議論した。
(1)避難のタイミングと持ち物
・何分で家を出られるか
・何分で車を出せるか
・持ち物、備蓄は何か
など
(2)車での避難場所・避難ルート
・避難ルートは、一方通行にするか
・事前にどんな準備が必要か
など
(3)高齢者等の避難支援
・誰が一緒に車に乗せるか(特に日中一人暮らし)
・逃げないと言う人をどうするか
など
第3回ワークショップ
25年2月22日、集合知形成のWSを実施した。集合知は、おおよそ、少数の専門家が考えるより、多様な人々がみんなで考えることが正しい、という考え方である。
これまでに出てきたアイデアを班単位で検討し、1位には5点、2位には4点……5位には1点、と点数をつけて、これを合算した。単に個々人が点数づけするだけでなく、話し合いにより合意することで、さらに気づきを深める効果を期待している。
最終的には次のような結論が得られた。
全体のコンセプト:
揺れがおさまったら即行動 動線行動 を想定しておく 24点
事前①:全員が避難場所、避難ルートを確認する 21点
事前②:高齢者に玄関に出てもらう、相乗り避難 22点
事前③:日ごろからのつながりづくり 18点
事前④:避難用具を玄関先に常備する 9点
直後①:家族に声掛け、安全確認 19点
直後②:5分以内に家を出る 10点
集合知以外の良いアイデアとして、「車は道路側に向けてとめる」などもあった。この結果を生かして地区防災計画素案作成へ向かうことにしている。引き続き、車による津波避難に取り組んでいきたい。
(参考文献)
・石垣市ホームぺージ「明和大津波から考えよう」(2021年11月5日)
≪https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/1/2/6821.html≫
・鍵屋一、西澤雅道「ワークショップと訓練で作る地区防災計画―石垣市白保地区を事例に―」地区防災計画学会誌第32号(2025年3月)
著者プロフィール
跡見学園女子大学教授
鍵屋 一 かぎや・はじめ
1956年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、東京・板橋区役所入区。法政大学大学院政治学専攻修士課程修了、京都大学博士(情報学)。防災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長、危機管理担当部長、議会事務局長などを歴任し、2015年4月から現職。災害時要援護者の避難支援に関する検討会委員、(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事、(一社)防災教育普及協会理事なども務める。著書に『図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ』(学陽書房、19年6月改訂)など。
★「自治体の防災マネジメント」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!
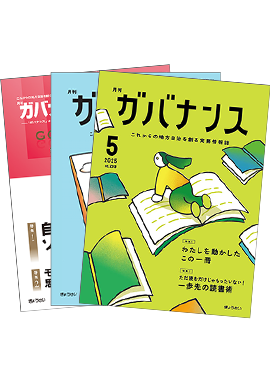
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫






















