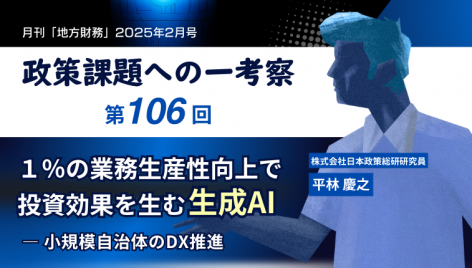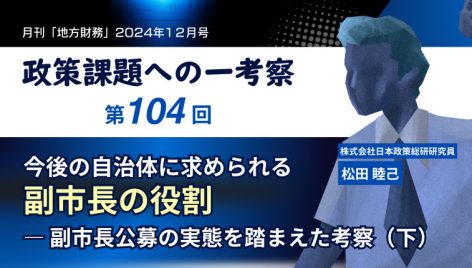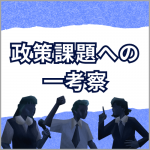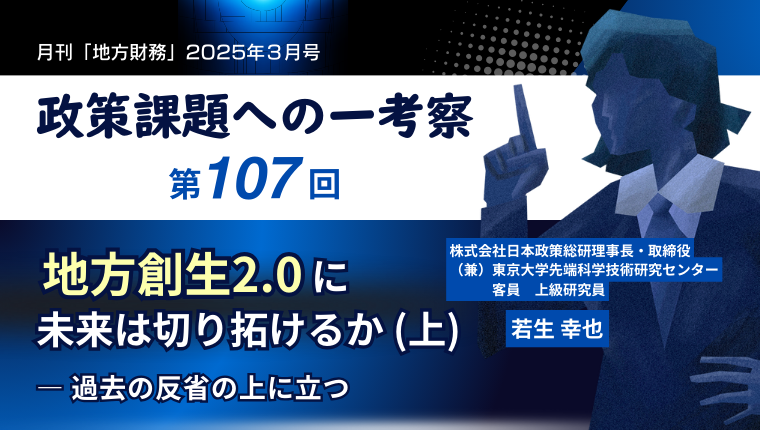
政策課題への一考察
地方創生2.0に未来は切り拓けるか(上) ― 過去の反省の上に立つ|政策課題への一考察 第107回
地方自治
2025.04.07
※2025年2月時点の内容です。
政策課題への一考察 第107回
地方創生2.0に未来は切り拓けるか(上) ― 過去の反省の上に立つ
株式会社日本政策総研理事長・取締役
(兼)東京大学先端科学技術研究センター客員 上級研究員
若生 幸也
(「地方財務」2025年3月号)
【連載一覧はこちら】
1 はじめに
地方創生政策が2014年に本格化して10年が経過した。2024年10月の石破内閣成立により、改めて「地方創生2.0」が打ち出された。地方財政的な文脈でも令和7年度政府予算案において「新しい地方経済・生活環境創生交付金」がこれまでの地方創生交付金1000億円の2倍である2000億円となり、注目を浴びている。
一方、この10年間の時間経過は残酷で、コロナ禍で一時的に緩んだものの大都市圏一極集中がより深化した状況にある。最新の「住民基本台帳人口移動報告2024年(令和6年)結果(1)」での転入超過は、東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)、山梨県、大阪府、福岡県の7都府県に限られる。この中でも特に東京都の転入超過は7万9285人と圧倒的で、神奈川県・埼玉県が2万人台で続く構図であり、地方創生当初から掲げられた「東京一極集中の是正」の目標はさらに実現が遠のいている。
〔注〕
(1)総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告2024年(令和6年)結果」令和7年1月
https://www.stat.go.jp/data/idou/2024np/jissu/youyaku/index.html
年代別に東京都の転入超過数を見てみると、20~24歳が最も多く8万6908人、次いで25~29歳が3万2065人であり、就職段階での転入が極めて多い。これと比べると進学段階での転入として考えられる15~19歳は2万827人と限定的である。すなわち、各地で育てられた学生が就職で東京圏に集中する構図が読み取れる。なお、進学段階で転入しても住民票を移さず就職段階で住民票を移す場合も56.4%と約半数強あることには留意が必要である(2)。
〔注〕
(2)総務省調査によると進学段階で引っ越しても56.4%は住民票を移さないとの結果がある点は留意が必要である。つまり15~19歳の転入が過小に、20~24歳の転入がやや実態よりも過大であろう。総務省「18歳選挙権に関する意識調査報告書」平成28年12月
https://www.soumu.go.jp/main_content/000461914.pdf
このように構造的に政策推進の難度も高まった地方創生に、“2.0” へのバージョンアップ可能性の有無を探り、地方自治体として未来を切り拓くために必要なことを考えたい。今号では、まずバージョンアップ可能性の有無を政府文書から探る。次号では地方自治体として未来を切り拓くために必要なことを描いてみたい。
2 地方創生2.0の基本的な考え方
政府はこれまでの地方創生の10年を振り返り、今後の地方創生2.0に向けた方向性を示した「地方創生2.0の基本的な考え方(3)」(以下「基本的な考え方」という) を2024年12月末に公表している。この中でも特に重要な要素を取り上げ、ここで整理したい。
〔注〕
(3)内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部「地方創生2.0の基本的な考え方(本文)」令和6年12月24日
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_chihousousei/pdf/honbun.pdf
(1)地方創生2.0起動の必要性
○ 我が国の成長力を維持していくためには、都市も地方も、楽しく、安心・安全に暮らせる持続可能な社会を創っていく必要。
○ 特に、人口減少が続く地方を守り、若者・女性にも選ばれる地方(=楽しい地方)、高齢者も含め誰もが安心して住み続けられる地方の構築は待ったなし。
○ 地方創生2.0は、単なる地方の活性化策ではなく、日本の活力を取り戻す経済政策であり、多様性の時代の国民の、多様な幸せを実現するための社会政策であり、我がまちの良さ、楽しさを発見していく営み。
○ それぞれの地域の「楽しい」取組が拡がっていくよう、次の10年を見据えた地方創生2.0を今こそ起動し、この国の在り方、文化、教育、社会を変革する大きな流れをつくり出していく。
第217回国会における石破内閣総理大臣施政方針演説(4)にも取り上げられ、話題となった「楽しい」という表現であるが、この基本的な考え方の中には「楽しい地方」が位置づけられている。文章内におけるイコールの位置を踏まえると、楽しい地方とは「人口減少が続く地方を守り、若者・女性にも選ばれる地方」を指す。米国ではトランプ政権による多様性・公平性・包括性(DEI)政策批判があるが、そもそも政策的進行が極めて遅れている日本において、ジェンダーギャップ解消を含めた多様性・寛容性の観点は地方において最も不可欠であろう。
〔注〕
(4)首相官邸「第217回国会における石破内閣総理大臣施政方針演説」
https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/0124shiseihoshin.html
一方、「日本の活力を取り戻す経済政策」として地方創生2.0を位置づけているが、大都市圏と地方圏の生産性格差を温存したまま、地方創生政策を推し進めても日本全体として活力を取り戻すこととは相応の距離がある。すなわち、「合成の誤謬(5)」を引き起こすおそれもある。この点が極めて難しい政策対応となることは間違いないだろう。
〔注〕
(5)ミクロの視点では合理的な行動であっても、それが合成されたマクロの世界では、必ずしも好ましくない結果が生じてしまうこと。
(2)これまでの取組の反省
○ 地方創生2.0は、これまで10年の反省をしっかりと踏まえたものでなければならない。例えば、
・ 若者・女性からみて「いい仕事」、「魅力的な職場」、「人生を過ごす上での心地よさ、楽しさ」が地方に足りないなど、問題の根源に有効にリーチできていなかったのではないか。
・ 人口減少がもたらす影響・課題に対する認識が十分に浸透しなかったのではないか。
・ 人口減少を前提とした、地域の担い手の育成・確保や労働生産性の向上、生活基盤の確保などへの対応が不十分だったのではないか。
・ 人口減少の進行、デジタル技術の進展を踏まえ、地方分権の評価、検証を含めた国と地方の役割のあり方について検討を行う必要があるのではないか。
・ 地方の課題が多様化・複雑化する中で、省庁間、自治体部局間の縦割りなど、情報やデータ、政策などの連携が不十分だったのではないか。
・ 産官学金労言の「意見を聞く」にとどまり、「議論」に至らず、好事例が普遍化されないなど、地方自らが主体的に考え行動する姿勢や、ステークホルダーが一体となった取り組み、国の制度面での後押しが不十分だったのではないか。
・ 地方創生交付金は、縦割り・単独事業が大半であり、小粒で補助金化しているのではないか。事業の効果測定や検証・改善が形式的だったのではないか。
この部分が「基本的な考え方」の中で最も重要である。過去の反省の上に立たない政策見直しは「海図なき航海」である。その意味で「基本的な考え方」の中で反省点に言及すること自体が高く評価されるべきである。また、例示列挙されている反省点は、概ね正確な問題認識に立っている。特に人口減少を前提とした取り組みの不足や国・地方の役割のあり方に関する検討の必要性認識は、真摯に2040年・2050年を見据えた地域政策を考えるときに不可欠な視点といえる。
1点、指摘することがあるとすれば、「産官学金労言」の位置づけである。この「お経」を唱えていれば救われるわけではなく、各地域の事情や取り組み分野、取り組みごとに必要な主体や役割も異なる。最も避けるべきは地域の顔役にあて職で「お経」の一員になってもらうことである。あくまでこれらの主体は例示であることを認識する必要がある。必ずしも全てを一体として揃える必要はなく、重要性・緊急性の高い問題や課題を解決するために、取り組みごとに一時的に編成されるチームや組織である「タスクフォース型」を前提に考えるべきである。
(3)地方創生2.0を検討していく方向性(6)
〔注〕
(6)内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部「地方創生2.0の基本的な考え方(概要)」令和6年12月24日
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_chihousousei/pdf/gaiyou.pdf
(基本姿勢)
・ 当面は人口・生産年齢人口が減少するという事態を正面から受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じていく。
・ そのために、「人を大事にする地域」、「楽しく働き、楽しく暮らせる地域」を創る。人手不足が顕著となり、人材や労働力が希少となるがゆえに、教育・人づくりにより人生の選択肢・可能性を最大限引き出すとともに、その選択肢を拡大していく。
・ 災害に対して地方を取り残さないよう、都市に加えて、「地方を守る」。そのための事前防災、危機管理に万全を期す。
(社会)
・ 「若者・女性にも選ばれる地方(=楽しい地方)」をつくることを主眼とする。
・ 賃金の上昇、働き方改革による労働生産性の向上、アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)の解消など魅力ある働き方・職場づくりを官民連携で進める。
・ 児童・生徒や学生が、地方創生の観点から我が町の魅力を再発見し、将来を考え、行動できる能力を重視する教育・人づくりを行う。
・ 年齢を問わず誰もが安心して暮らすことを可能とする、医療・福祉等の生活関連サービス、コミュニティの機能を維持する。
(経済)
・ 文化・芸術・スポーツなどこれまで十分には活かされてこなかった地域資源を最大限活用した高付加価値型の産業・事業を創出する。
・ これまで本格的に取り組んで来なかったDX・GXなどの戦略分野での内外からの大規模投資や、域外からの需要の取り込みを進め、地域の総生産を上昇させる。
・ 観光等の地域に密着した産業やサービスを支える教育・人づくりを進める。
(基盤)
・ GX・DXインフラの整備を進め、NFTを含むWeb3.0など急速に進化するデジタル・新技術を最大限活用する。
・ 地方と都市の間で、また地域の内外で人材をシェアし、人・モノ・技術の交流、分野を超えた連携・協働の流れを創る。
(手法・進め方)
・ 政策の遂行においては、適切な定量的KPIを設定し、定期的な進捗の検証と改善策を講ずる。
これまでの取り組みの反省が概ね正確になされているため、地方創生2.0を検討していく方向性も概ね重要な要素が盛り込まれている。もちろん要素でしかなく、具体的な地方創生2.0を実現するための施策・事業の構築は極めて難しい。なお、この方向性の後には基本構想の5本柱があるが、まだ明確化した政策のタマは限定的であるため、本稿では割愛する。
ここで注目すべきは、「急速に進化するデジタル・新技術を最大限活用する」点にある。デジタル田園都市国家構想交付金では、特にTYPE1(優良なモデル・サービスを活用した実装の取り組み)では様々なデジタルツールの導入が進み、優良事例の横展開パターンでは概ね有効に機能したと評価できる。一方、TYPE2、3のデータ連携基盤を活用した複数サービスの実装を伴う取り組みでは、各取り組みの効果も限定的で、かつ将来的な運用費用を見据えず過剰な投資費用を計上して持続可能性に欠ける取り組みも見られた。デジタル・新技術を最大限活用するとしても、重要な点は「持続可能性」にある。Web3.0も地域DXの文脈では具体的な優良事例がそれほど積み上がっておらず、このように言及するレベルとはいいがたい。
3 おわりに
本稿では、地方創生2.0に未来を切り拓けるかを検証するために、まずは政府文書である「基本的な考え方」を整理した。少なくとも、本稿の副題である「過去の反省の上に立つ」ことはできていると評価できる。一方で、人口減少に立ち向かう情勢は刻一刻と悪化している。本稿執筆時点で埼玉県八潮市の道路陥没問題がまだ解決していない。人口減少下の土木・公共施設マネジメントはどうあるべきか。突きつけられた課題は重い。次稿では、地方自治体として地方創生2.0に向き合い、未来を切り拓くために必要なことを素描したい。
〔参考文献〕
・若生幸也「改めて未来を描き『動く』仕組みを設計する」『月刊地方財務(2019年1月号)』2019年1月、ぎょうせい。
https://researchmap.jp/twakao/misc/19531134
・若生幸也「地方創生2.0に向けて、これまで地方創生についてメディアで何を発言してきたか」
https://note.com/twakao/n/n67aa85e43bca?sub_rt=share_pw
*政策コンテンツ交流フォーラムは、株式会社日本政策総研、神戸シティ法律事務所が連携ハブとなり、国・地方自治体・民間企業のメンバーを架橋し、政策的課題を多面的に検討するネットワークです。本コラムを通じて、フォーラムにおける課題認識、政策創造の視点等をご紹介します。
本記事に関するお問い合わせ・ご相談は以下よりお願いいたします。
株式会社日本政策総研 会社概要
コンサルティング・取材等に関するお問合せ先
https://www.j-pri.co.jp/about.html