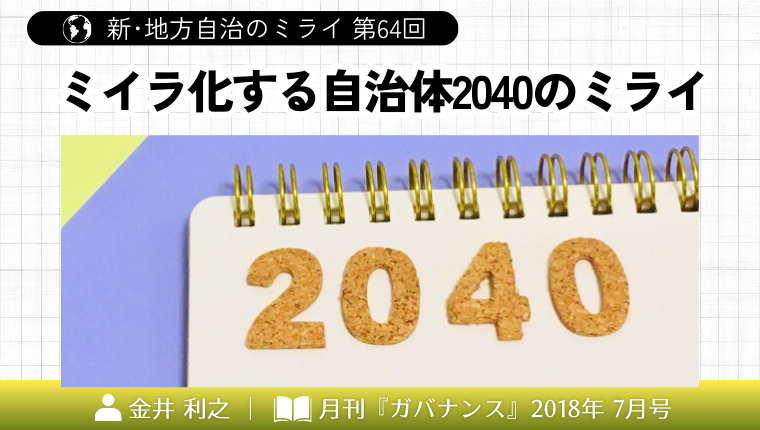
新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第64回 ミイラ化する自治体2040のミライ
地方自治
2024.10.30
本記事は、月刊『ガバナンス』2018年7月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
はじめに
東京五輪の2020年開催後に経済不況が懸念されるところである。さらに、その後も、戦後ベビーブーマー世代が後期高齢者になる「2025年問題」や、AIの進展に拠って根本的に世界が変わる「技術的特異点(シンギュラリティ)」が2045年頃などと言われている。もちろん、以前からこうした「未来予測」はありふれたもので、「ノストラダムスの大予言」または「2000年問題」などがあった。いわゆる第1次増田氏報告の「地方消滅」も、2040年段階での女性人口減少予測である。
自治体及び自治制度は、ある意味で最先端であり、最末端である。国が対策を放置した人口減少も高齢化も、地域に不均衡に発生するため、先端自治体は課題に早く対処をしている。国が政策転換したときにも、現場で執行する役割を担わされるのは末端自治体である。その意味で、自治体及び自治制度が長期展望を持つことは重要である。
政策の末端を担う自治制度を所管する総務省が、「自治体戦略2040構想研究会」を立ち上げたのは、時宜に適ったものであろう。2018年4月には『第一次報告~人口減少下において満足度の高い人生と人間を尊重する社会をどう構築するか~』(以下、『報告』)がとりまとめられているので、今回は『報告』を検討してみよう。なお、研究会はその後も検討作業を続けている。
2040年からの逆算?

『報告』によれば、人口減少など様々な変化が予測されるなかで、これまでの「人口増加を前提としてきた制度や運用は、人口減少下では、そのまま適用しても所期の効果を発揮できない可能性が高い」ので「人口増加モデルの総決算を行い、人口減少時代に合った新しい社会経済モデルを検討する必要がある」という。そこで、「過去からの延長線で対応策を議論するのではなく、将来の危機とその危機を克服する姿を想定した上で、現時点から取り組むべき課題を整理」して「バックキャスティングに検討する」方策を採った。その際、「高齢者人口がピークを迎える2040年頃に想定される課題」に焦点を当てたのである。
もっとも、(1)子育て・教育、(2)医療・介護、(3)インフラ・公共施設、公共交通、(4)空間管理、治安・防災、(5)労働・産業・テクノロジーという5個別分野に関する自治体行政の課題(『報告』Ⅱ章)は、新味はない。
人口減少に伴って職員数は減少し、少子高齢化・生産年齢人口減少が進行し、税収減少と社会保障支出増加により地方財政が厳しくなる。三大都市圏・連携中枢都市圏・定住自立圏域人口が大半となる。臨時・非常勤職員が増え、公共サービス提供主体は多様で多元的な主体(住民団体・NPO・企業など)となる「新しい公共空間」(注1)をいかに豊かにするかが重要という。いずれも、これまでの議論の延長線上である。
注1 総務省『分権型社会に対応した地方行政組織運営の刷新に関する研究会報告書』(2006年)という、小泉政権期の懐かしい報告書が注記されている。
2040年頃にかけて迫り来る危機
『報告』で重要なのは、2040年頃にかけて迫り来る内政上の危機である(Ⅲ章)。第1は、「若者を吸収しながら老いていく東京圏と支え手を失う地方圏」である。もっとも、これは第1次・第2次増田氏レポートが指摘してきた点であり、「地方創生」が展開された。結局、「地方創生」が無意味だったことを総務省が表明したのだろう。
第2は、「標準的な人生設計の消滅による雇用・教育の機能不全」である。戦後日本の世帯主雇用モデルは崩壊して、就職氷河期世代の高齢化が社会全体にとってのリスクとなる。人間的な付加価値を求められる労働力が不足するし、求められる資質・能力も大きく変化する。つまり、人口減少するが、対応できない人間が増える、という危機である。
要するに、国民は経済成長(及び次世代人口)を生むための人的資源(人財)である、と位置づけるのであるが、この発想はまさに戦後成長国家の延長線上の発想であろう。もちろん、『報告』は「満足度の高い人生と人間性を尊重する社会」が目的であり、経済を適切に運営することは手段にすぎないはずである。しかし、『報告』を見る限り、経済に奉仕する雇用・教育が機能不全になることが、なぜ、人生の満足度と人間性の尊重にマイナスに繋がるのかは説明されていない。
第3は、「スポンジ化する都市と朽ち果てるインフラ」である。もっとも、戦後日本は一貫してスプロールなので、ランダムで無秩序な都市空間は新しいことでもない。また、公共施設やインフラの老朽化は、「公共施設マネジメントの一層の推進」(2016年11月7日付総務省財務調査課長通知)など、既に広く指摘されてきたことである。
危機の常態化

つまり、『報告』も指摘するように、2040年の危機は「現時点で既に想定されている」。その意味で、矛盾が不気味な沈黙のなかで蓄積して、2040年に一気に危機として暴発するのではない。「2040年頃にかけて迫り来る」と表記されているように、過去・現在・未来と緩慢に連続して、課題も継続的に累積し続ける。もっと言えば、2040年を超えても半永久的に続くのであろう。楽観的に『報告』は、「顕在化してから対応するのでは遅い」というが、既に先端の自治体現場では顕在化していよう。
また、『報告』は、「こうした危機をうまく乗り越えることができれば、わが国は世界に先駆けて、人口減少に対応した社会経済のモデルを発信する好機となり得る」(48頁)と楽観的に展望する。
しかし、そもそも、地域社会における人生と人間を預かる先端行政の自治体としては、世界に「モデルを発信する」などという国威発揚は、どうでもよい話である。また、2040年に「乗り越える」(注2)危機の山が到来するのではなく、2040年を超えても慢性的に危機は続く。それは、危機の常態化・日常化なのであり、そもそも危機ではなく「当たり前」になるのかもしれない。将来に向けてしばらく頑張れば何とかなる、という発想自体が総決算されるべき人口増加社会のスキーマなのかもしれない。
注2 人口減少は急坂を転げ落ちるような常態なので、危機を「乗り越える」という右肩上がりで表現すること自体、人口増加社会の知的呪縛かもしれない。
おわりに~自治体戦略の基本的方向性
高度経済成長モデルの総決算が必要とはいえ、『報告』は各行政分野での具体的な取組みを示すわけではない。「各府省の施策(アプリケーション)の機能が最大限発揮できるようにするための自治体行政(OS)の書き換え」(49頁)や、「全ての府省が政策資源を最大限投入するに当たって、地方自治体も、持続可能な形で住民サービスを提供し続けられるようなプラットフォーム」(49頁)を提示するだけである。自治体は末端行政である。
とはいえ、『報告』で示される基本的方向性に新味はない。自治体を「単なる『サービス・プロバイダー』から公・共・私が協力し合う場を設定する『プラットフォーム・ビルダー』へ」(49頁)転換する発想は、既にありふれた話である。人口減少のなかで「フルセット主義を排し」「自治体間で、有機的に連携することで都市機能等を維持確保する」という広域化・圏域化の処方箋も、月並みな話である。要するに、多様な主体や自治体間の連携・協働や標準化・共同化という、戦後も一貫して進められた発想の延長線上である。唯一の新しさは、「自治体行政の新たな姿を描く際には、ICTや郵便、統計などを含め、その総力を挙げて、有機的に連携」することである。しかし、これは2001年中央省庁再編で総務省が設置されたことを意味しているだけである。
『報告』の問題意識は重要に思われるが、従来モデルを転換する構想にまでは至っていないようである。『第二次報告』に向けて検討が進められる際には、新たなモデルを提示するのか、これまでの延長線上の対策を示すのか、興味あるところである。ミイラ化した自治の思考枠組みを超えて、大いに知恵を絞ってもらいたい。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。























