■オープンデータをどう活用するか
──現在のオープンデータやビッグデータをめぐる動きを教えてください。
オープンデータという言い方は、アメリカが使い始めたもので、政府の保有するデータを一般の人にも公開し、それを自由に使って、企業に業務革新や新市場を開発してもらったり、NPOのまちづくりに役立ててもらうことを意図している。オバマ政権の初期のころ、マイクロソフトに政府が保有する衛星のデータや気象観測データなどを無償で提供した。マイクロソフトは、アジュールというクラウドコンピューティングを使ってデータを分析し、竜巻の移動の予測などをスマートフォンに流すというトライアルを行った。そういう高度な分析を政府でやろうと思っても、人員も含めて難しいので、民間の力を借りる。民間側も新しいサービスのトライアルをできた。
一方、ローカルガバメントでは、サンフランシスコなどで、例えば、道路の敷石がはがれているとスマートフォンからウェブにアクセスして通報するような取り組みを行っている。また、市の保有データを企業に無償で与え、道案内をするアプ リやコンシェルジュ機能を持った準公共的なアプリを開発してもらった。今までなら役所がそういうシステムを運用管理しなければならなかったが、データを出すことにより、タダでやってもらう。役所としては雇用は増えるし、納税者も増えるので、そのほうがいいという発想だ。
──日本ではどうか。
自治体で同じセンスで取り組んだのが鯖江市や武雄市だろう。国では、内閣官房や総務省、経済産業省などが熱心にやろうとしている。ただデータをどんどん出すところまでには至っていない。オープンデータについては、G8合意(オープンデータ憲章)があるので進むと思う。だが、どの範囲でやるか、どういう形でやるかは、各国各様。フランスは各省庁のデータ形式を標準化しないが、デンマークは集めたデータの形式を整え、使いやすいようにして出すと言っている。
── 個人情報の問題などはないですか。
日本では自治体も政府も統計データの延長のようなものになると思うので、その限りでは問題ない。ただ、企業が本当に使いたいデータは、個人個人の動きをつかめるマーケット情報だ。その場合、パーソナルデータをどう使うか、どうやって 個人情報を守るかを検討する必要がある。
■マイナンバー制度で自治体間格差が広がる
──マイナンバー制度について、各自治体で準備が進んでいるが、温度差があるのではないか。
住基番号に代わってマイナンバーを付番することについては準備が進んでいると思う。だが、税と社会保障との関係や災害時の被災者救済などの関係について、どうシステムを連動させ、どう使っていくかというところまで、関係部局の人に情報 が行きわたっていないのではないか。特に福祉系や災害系の人たちには伝わっていないと思う。
一方で、例えば東京都三鷹市のように、首長が熱心にやろうとしている自治体では、全庁的に意識が高まっているように感じる。また、甲府市では、すでに統合データベースを持っている。各基幹システムのデータが符号され、総合窓口化も実現している。だから、マイナンバー制度への対応はかなり容易だ。
自治体は条例を改正することで、独自にさまざまなことができるので、サービス面で差が出てくると思う。千葉県柏市では、介護サービス事業者とデータの連携を図ることで、介護や在宅療養などに対応していくことなども検討している。新しいまちづくりの一環という位置付けだ。
ただ、今のところそこまで思い当たらない自治体が大部分だし、たとえ意識の高い担当者などがやろうと思っても、内部だけでなく外部との連携も必要になる。もちろんそれには首長レベルの判断が必要となり、首長を説得するのは大変だから、やめてしまおうと思うかもしれない。だからその差は大きくなっていくのではないか。
■問われる現場の企画力
──マイナンバー制度への対応なども含めて自治 体職員にメッセージがあれば。
マイナンバー制度による業務革新については、3年後の利用範囲の見直しで全行政分野の業務に波及することが目に見えている。そうなると、現場の企画力が問われることとなり、特に中堅や若手の人たちのやりがいにつながると思う。
官民連携の動きも3年後には見直しされる。いまでも条例さえ変えれば、その行政区域内ではできるが、全面的にできるようになる。そうすると自分の仕事や組織、各現場の関係づけなどが変わる可能性が高い。だからこそ、よく勉強して、何ができるか、そのためには何からまず手をつけな ければいけないかということを考えてほしい。30 ~ 40 代の係長級くらいの人たちが即戦力になるはずだから、今から期待している。
医療や福祉の関係なども近い将来、変わってくると思う。さらに、財務省でも銀行口座に番号をふる検討を進めている。各世帯の預金残高を把握し、有価証券の取得額や自治体が持っている不動産の情報も吸い上げて、新しい税制を考えているようだ。そうすると、不正はしにくくなる。また、今までは資産がほとんどなく、年金しか現金収入がない人でも、資産がある人と同じ課税の仕組みだった。今度は資産を持っている人の情報を集めて分析し、その人には新たな課税をする。一方で、資産がない人は、社会保障や医療費などの負担を下げていくといった戦略をとっていくと思う。
──健康増進や予防の取り組みによって医療保険に差をつけるような議論も出ている。
そうしないと、2025 年以降には団塊の世代が75 歳以上の後期高齢者になるし、2050 年には65歳以上の高齢者の比率が40%になる中で、財政がもたない。それをみんなで共有して、財源を確保したうえで、どう使っていくかということを本気でデザインする必要がある。自治体の人たちも、その中で中心的役割を担うことになる。大きい仕組みの話は国でやるが、その地域をどうつくっていくかは自治体の仕事。首長も含めて自治体で働く人たちのやりがいにもなると同時に、責任も重いということだ。
いずれにしろ3年後に変わることはわかっているのだから、背中をつつかれながら、ついていくのではなく、自分がもっといい方向に変えてやろうという思いで行動してほしい。
写真/五十嵐秀幸
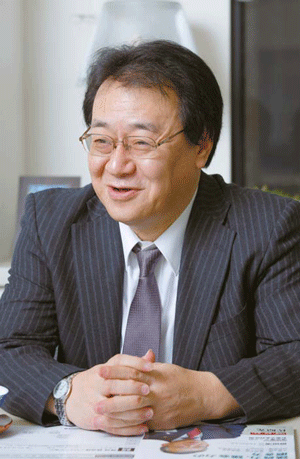
1955 年生まれ。東京大学大学院経済学研究科博士課程修了、経済学博士(東京大学)。現在、東京大学大学院情報学環長・大学院学際情報学府長、国立情報学研究所客員教授、一般社団法人次世代放送推進フォーラム(NexTV-F)理事長。総務省情報通信審議会情報通信政策部会長(2011 ~)、総務省「地方公共団体における番号制度の活用に関する研究会」座長(2011 ~)などを歴任。『Digital Economy and Social Design, Springer Verlag』(編著)、『複合的ネットワーク社会』(有斐閣)など著書多数。